静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階


ここでは準備書面を掲載させていただきます。下記よりご覧いただければ幸いでございます。
>>浜岡原子力発電所運転永久停止請求事件の準備書面(ダウンロードはこちら)
平成23年(ワ)第425号・474号・745号
浜岡原子力発電所運転永久停止請求事件
平成24年(ワ)第76号
浜岡原子力発電所運転永久停止請求事件
原 告 清水澄夫外 180名
被 告 中部電力株式会社
準 備 書 面(1)
2012年3月5日
静岡地方裁判所浜松支部民事部合議A係 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 田 代 博 之
弁護士 小 林 達 美
弁護士 大 橋 昭 夫
弁護士 森 下 文 雄
弁護士 塩 沢 忠 和
弁護士 杉 山 繁二郎
弁護士 阿 部 浩 基
弁護士 久保田和之
弁護士 池 田 剛 志
弁護士 杉尾健太郎
弁護士 靍 岡 寿 治
弁護士 小 池 賢
弁護士 鈴 木 淳
弁護士 平野晶規
弁護士 加 茂 大 樹
弁護士 末 永 智 子
弁護士 山 形 祐 生
目 次
| 第1 原発差止めの法理と主張立証責任 | 3頁 |
| 第2 浜岡原発の危険性 | |
| 1 故障想定の有り方(単一故障の想定で足りるか、 共通原因故障を想定すべきか) | 8頁 |
| 2 マークⅠ型格納容器の欠陥 | 15頁 |
| 3 使用済み核燃料プールの破損の危険性 | 16頁 |
| 4 地震と耐震設計 | |
| (1)地震国日本に原発はつくるべきではない | 16頁 |
| (2)基準地震動Ssは予想される最大の地震動となっているか。 | 18頁 |
| (3)耐震上の余裕について | 21頁 |
| (4)制御棒挿入失敗の危険性 | 25頁 |
| (5)津波 | 26頁 |
| (6)地震時地殻変動 | 31頁 |
| (7)地震学と防災のあり方 | 33頁 |
| 5 地盤 | |
| (1)基盤岩 | 40頁 |
| (2)活断層・H断層 | 41頁 |
| 6 本件原子炉施設の老朽化 | |
| (1)SCC(応力腐食割れ) | 44頁 |
| (2)配管の減肉現象 | 52頁 |
| (3)中性子照射脆化 | 55頁 |
| 59頁 |
静岡地方裁判所に係属した浜岡原発に係る平成15年(ワ)第544号,平成16年(ワ)第9号原子力発電所運転差止請求事件の2007年10月26日判決は,原,被告の主張立証責任について「原子炉施設の内包する危険性,原子炉の利用に対する国の規制及びその保護法益に加え,原子炉施設の安全設計,安全管理等に関する資料の大部分を被告が保有し,証拠が偏在していること,企業秘密等の制約があるため原告らが立証に必要な資料を入手することが困難であることなどの事情に照らせば,被告は,当該原子炉施設が原子炉等規制法及び関連法令の規制に従って設置,運転されていることについてまず主張立証する必要があり,被告がその主張立証を果たさないときは,人格権侵害の具体的危険性の存在を推認するのが相当である。そして,被告が原子炉等規制法及び関連法令の規制に従って当該原子炉施設を設置,運転していることを立証したときは,原則どおり,原子炉施設の運転差止を請求する原告らにおいて,上記国の諸規制では原子炉施設の安全性が確保されないことを具体的に根拠を示して主張立証すべきである。」と判示する。
静岡地裁判決は,「被告が原子炉運転規制法及び関連法令の規制に従って当該原子炉施設を設置,運転」していることの主張立証に成功すれば,原子炉についての一応の安全性を具備していることが認定され,原告において,具体的危険性を主張立証すべきだと判示するが,このような観念的な主張立証の責任の分配の思考方法は行政訴訟として提起された伊方原発の原子炉設置許可処分取消請求訴訟の最高裁判所判決(1992年10月29日)の判断の枠組に固執し墨守しているものであって,到底,民事訴訟としての原発差止めの法理にはなりえず,現時点では大いに反省されなければならない。
従来,静岡地裁の前記判決や,同種の原発差止めをめぐる多数の判例で原子炉の具体的危険性の主張立証責任が原告側にあるとされ,このことが結果的に原告側に過大な立証を課すことになり,訴訟の場が科学・技術論争の場に陥り,原告側より圧倒的に経済的にまさる被告側を免罪してきたものである。
従来,原子炉の安全性の程度は,社会的に許容される程度の安全性を備えていることを意味する「相対的安全性」で足りるとされていたが,現在では,そのような考え方は採りえない。
原子炉の設置,運転によって,過酷事故を発生させない,それらの過酷事故によって環境や周辺住民の生命,身体,財産に被害を及ぼす確率がほぼないという「絶対的安全性」に近似する考え方により,被告側に主張立証を求めることが現代的な訴訟法理であり,そのことが今まさに必要不可欠である。
中央防災会議が2011年9月28日に取りまとめた「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告」は,「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震,津波を検討」し,「発生頻度は極めて低いものの,甚大な被害をもたらす最大クラスの津波」を想定すべきであるとしており,又,原発の耐震安全性を検討する国の作業部会の主査と委員を2011年7月末日に辞任した纐纈一起東京大学教授も,毎日新聞のインタビューにおいて,「立地を問わず,過去最大の揺れと津波を同じ重みをもって安全性を考慮するよう改めるべき」であり,「過去最大というのは,原発の敷地で,これまでに記録したものではなく,日本,あるいは,世界で観測された最大の記録を視野に入れることが重要である。」と述べている。
地震対策,津波対策については,多くの学者が,人間が認識できる過去において生じた最大の地震,最大の津波,いわゆる「既往最大」の考え方に立脚して対策をとるべきだと主張している。
そして,最大の地震,最大の津波を前提にした安全対策をとらなければ,原発の安全性は確保されたとはいえないとしている。
前記報告や学者の見解に待つまでもなく,原告側に課せられるとする具体的危険性の主張立証の程度は,被告側の前記の安全性の主張立証の程度に対応するものであり,最早,具体的危険性というよりも,抽象的危険性に近似するものであり,それでほぼ足りるものと考えなければならない。
環境に放出された放射性物質は広範囲に広がり,今も周辺住民ばかりか,日本列島に居住する多くの人々に苦痛を与えている。
今まで,東京電力は勿論のことであるが,被告も又,浜岡原発では過酷事故は発生しないものと考え,静岡地裁における前記先行訴訟においても,被告は,そのような見地から訴訟の追行をしてきた。
過酷事故対処を免れるための確率論としてアメリカのラスムッセン報告が有名である。
アメリカ原子力委員会は,マサチューセッツ工科大学のノーマン・ラスムッセン教授を主査としたグループに確率論的手法を用いた原子炉の安全性評価を命じ,その報告をもとに,同委員会は,1975年,「原子炉安全性研究」を公表した。
それによると,過酷事故発生の確率は,極めて小さく,「原発事故で人が死亡する確率は,航空機墜落によって,地上で人が死ぬ確率よりも大幅に低い。」と結論づけられ,以後,過酷事故問題は蓋をされてしまったという。
しかしながら,この確率論にはアメリカ国内でも批判が多く,地震動などで多くの部品が一斉に破損する「共通原因故障」等も考慮されておらず,およそ科学的とはいえなかった。
しかし,この過酷事故発生の確率は極めて低いとするラスムッセン報告は,世界に安全神話を広める役割を果たし,わが国にも大きな影響を与えた。
今までのわが国における原発訴訟においても,被告の主張する安全神話に裁判所が従い,およそ過酷事故は発生しないとの考え方のもとに主張立証責任が組み立てられ,その結果,原告側に過重な主張立証責任が課されることになったものである。
本件は,平和的生存権,環境権,人格権に基づく差止め請求の訴であって,その審理の対象は,原発において過酷事故が発生する具体的危険性の有無であって,当該原発の設置許可自体の当否ではない。
先行した原発裁判において,電力会社は,原子力物理学,材料学,機械工学,流体学,電気工学,地震学,地質学,変動地形学等の知識をくりひろげた結果,これが原告ら住民に比べ,圧倒的な力を有する電力会社側に有利に作用し,ことごとく電力会社が勝訴してきたものである。
原発裁判において科学論争,技術論争を否定するものではないが,社会的にみて,被告ら電力会社が原告ら一般の住民が納得できる安全対策をとっているのか否かという視点が大切にされなければならないし,決して科学的真実を求めることに重点がおかれてはならない。
こうした科学論争,技術論争の偏重が,福島第1原子力発電所の過酷事故をもたらした1つの要因になったことは今や明白で,福島第1原子力発電所の過酷事故の経験後に裁判所が旧態依然とした従来の主張立証方針を原告側に押しつけることは到底許容されるものではない。
その意味で,「原告において具体的危険性を具体的に主張立証し,その上,原告についてもどのような被害が生ずるのか因果関係についても具体的に主張立証すべきである。」とする被告の冒頭指摘の主張は排斥されなければならない。
ましてや,今回の福島第1原子力発電所の過酷事故は,環境に大きな被害を与えたもので,あわせて,その周辺に居住する住民は勿論のこと,広範囲にわたって莫大な被害を与えたものであり,いずれの原告にどのような被害が生ずるのか,その因果関係についても具体的に主張立証する必要があるとする被告の主張は極めて妥当性を欠くものである。
上記過酷事故は,原告らが個々の被害について,その因果関係を含め特段の立証をしなくとも公知の事実であることを明白にしているものである。
(1)従来の安全規制に関する考え方(総論)
① 指針
原子力発電所などの原子炉施設は,原子炉等規制法や電気事業法等によって設置段階,運転段階など各段階において,安全のための規制がなされてきた。
まず,設置段階では,経済産業省の設置許可を得なければならず(原子炉等規制法23条1項),その際,原子力安全委員会の意見を聞かなければならないこととされている(同法同条2項)。そして,原子力安全委員会は次の指針をそれぞれ定めている。
ア 安全設計審査指針
原子力安全委員会が,発電用軽水炉型原子炉(軽水炉)の設置許可申請に係る安全審査において,安全性確保の観点から設計の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的として定めたもの。
イ 安全評価審査指針
原子力安全委員会が,軽水炉の設置許可申請に係る安全審査において,原子炉施設の安全評価の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的として定めたもの。
ウ 耐震設計審査指針
原子力安全委員会が,軽水炉の設置許可申請に係る安全審査のうち,耐震安全性の確保の観点から耐震設計方針の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的として定めたもの。
② 上記安全設計審査指針等は,一般平常時だけでなく,機器の故障や誤動作,地震や地震以外の自然現象等の異常発生時においても,一般公衆ないし従事者に対して放射線被ばくによる障害を与えず,また,事故時においても一般公衆ないし従事者の安全が確保されることを基本方針としている。
そして,上記安全設計審査指針等は,数度の見直し,改訂を経ており,原子炉施設の安全性は確保されてきたものと考えられてきた。
(2)福島第1原発事故の発生と従来の安全規制に関する考え方の誤り
① しかしながら,このような安全規制にもかかわらず,2011年3月11日午後2時46分,三陸沖を震源とするマグニチュード9.0を記録した東北地方太平洋沖地震が発生し,それにより福島第1原発事故が発生した。
② 上記福島第1原発事故の発生を防ぐことができなかったのは何故か。それは,上記安全設計審査指針及び安全評価審査指針の中では,地震という共通の原因に基づく故障を全く考慮していなかったからである。
ア すなわち,安全設計審査指針は,「Ⅷ.安全保護系」「指針34.安全保護系の多重性」において「安全保護系は,その系統を構成する機器若しくはチャンネルに単一故障が起きた場合,又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合においても,その安全保護機能を失わないように,多重性を備えた設計であること」などと規定しているように,単一故障を仮定してもその安全機能を損なわない設計であることを要求している。
また,安全評価審査指針は,「Ⅱ.安全設計評価」「5.解析に当たって考慮すべき事項」「5.2安全機能に対する仮定」において「⑵解析に当たっては,想定された事象に加えて,『事故』に対処するために必要な系統,機器について,原子炉停止,炉心冷却及び放射能閉じ込めの各基本的安全機能別に,解析の結果を最も厳しくする機器の単一故障を仮定した解析を行わなければならない。この場合,事象発生後短期間にわたっては動作機器について,また,長期間にわたっては動的機器又は静的機器について,単一故障を考えるものとする。」などと規定しているように,各事象の解析に当たって,想定される事象に加え,作動を要求される安全系の機能別に結果を最も厳しくする単一故障を仮定することを要求している。
イ このように,上記安全設計指針等は,原子炉施設を運転していく上で不可避的に発生する可能性のある故障その他の異常事象のみを想定して,その場合においても原子炉施設の安全性が確保されていることを要求しているに過ぎなかった。このたびの東北地方太平洋沖地震のような巨大地震その他の自然現象に対するものとしてこれを要求しているものではなかったのである。
ウ そして,地震その他の自然現象に対しては,安全評価審査指針に基づく安全評価とは別に,耐震設計審査指針等の基準を満たすことが要請され,この基準をもって,安全性が確保されると考えられていたのであり,そこでは,想定すべき地震その他の自然現象の規模が決定され,想定以上の地震等が発生することは考慮しなくてもよいこととされていたのである。
エ しかしながら,従来の安全規制に関する考え方を前提としても,地震や津波等の自然現象については知見がいまだ十分ではなく,想定を超える地震等が起きる可能性は十分にあると指摘されてきた。このことは,耐震設計審査指針においても,同2頁の「(解説)Ⅰ.基本方針について⑵『残余のリスク』の存在について」で「地震学的見地からは,上記⑴のように策定された地震動を上回る強さの地震動が生起する可能性を否定できない。このことは,耐震設計用の地震動の策定において『残余のリスク』(策定された地震動を上回る地震動の影響が施設に及ぶことにより,施設に重大な損傷事象が発生すること,施設から大量の放射性物質が放散される事象が発生すること,あるいはそれらの結果として周辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼすことのリスク)が存在することを意味する。したがって,施設の設計に当たっては,策定された地震動を上回る地震動が生起する可能性に対して適切な考慮を払い,基本設計の段階のみならず,それ以降の段階も含めて,この『残余のリスク』の存在を十分認識しつつ,それを合理的に実行可能な限り小さくするための努力が払われるべきである。」と示されているところである。
そして,このような地震や津波等の自然現象によって,安全系に属する各系統が故障する可能性は高く認められる。そして,この場合の故障は,地震や津波等という共通した原因によって生じるものであるから,同時に複数の箇所が故障するという可能性も十分あるということを考えなければならないという指摘も従前からなされてきた。すなわち,安全設計審査指針や安全評価審査指針を定める段階において,地震や津波その他の自然現象による共通した原因による同時故障を仮定した安全審査を行わなければならないということである。
しかしながら,かかる指摘は,「安全評価審査指針に基づき,地震その他の自然現象に対し別途設計上の考慮がされることを前提として,内部事象としての異常事態について単一故障の仮定(単一箇所の不具合の想定)による安全評価をする方法をとっており,その方法自体は不合理ではない。原子炉施設においては安全評価審査指針に基づく安全評価とは別に耐震設計審査指針等の基準を満たすことが要請され,その基準を満たしていれば安全上重要な設備が同時に複数故障するということはおよそ考えられないから,耐震設計審査指針等の基準を満たしていることに加えて,さらに地震発生を共通原因とした故障の仮定をした安全評価をする必要は認められない。」(先行訴訟である静岡地方裁判所平成15年(ワ)第544号の判決)などとして考慮されることはなかった。
(3)東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会作成の2011年12月26日付け「中間報告」
しかしながら,福島第1原発事故をうけて作成された上記「中間報告」は,過酷事故対策に関して,「設計上の想定を大きく上回る津波の場合,共通的な要因によって安全機能の広範な喪失が一時に生じることがあり,直ちにシビアアクシデントに至る可能性が高い。しかし,これまで,設計基準を超える事象を扱うシビアアクシデント対策においては,津波のリスクが十分には認識されていなかった。」と報告し,地震その他の自然現象に対して,従来の安全審査が不十分不適切であったことを明確に指摘している。
(4)事故調査委員会での班目委員長の発言
① 2012年2月25日,国会において,4回目の東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)が開かれ,参考人として原子力安全委員会委員長の班目春樹氏が次のとおり発言した。
「原子力安全委員会というところは,原子力安全の確保に関する基本的な考え方を示すということが最大の任務となっております。したがいまして,そういうものを安全審査指針類としてこれまで発行してきたわけでございますが,今まで発行してきた安全審査指針類にいろいろな意味で瑕疵があったということは,もうこれははっきりと認めざるを得ないところでございます。例えば,津波に対して十分な記載がなかったとか,あるいは全交流電源喪失ということについては,解説の中に,長時間のそういうものは考えなくてもいいとまで書くなど,明らかな誤りがあったことは認めざるを得ないところで,大変,原子力安全委員会を代表しておわび申し上げたいと思っております」。
「本来,安全確保の一義的責任は,あくまでも電力会社にあります。したがって,電力会社は,国がどういう基準を示そうと,その基準をはるかに超える安全性を目指さなければいけないんです。それなのに,それをしないで済む理由として安全委員会がつくっているような安全審査指針類が使われているとしたら,大変心外だと思いますし,これからは決してそうであってはならないというふうに思っております。」
② このように,従来の安全審査指針類が原子力安全確保の観点から不十分なもので誤りであったことは,原子力安全委員会の委員長自らが国会で認めている。
(5)小括
以上のように,従来の安全設計審査指針等の安全審査においては,地震等の自然現象による安全系の同時多発的な損傷は全く考慮されてこなかったのであり,想定し得るあらゆる過酷事故を防止できるものとはなっていなかった。従来の指針そのものが間違っていたのであるから,同指針は早急に見直される必要があり,従来の指針での審査に通ったからといって安全性が確認されたとはいえないのである。
巨大な地震や津波等の自然災害による安全系の故障は,複数の箇所が同時に故障する可能性が高いことは現時点において十分認識されるに至っており,共通原因に基づく故障を仮定した安全評価が行われなければならないことは明らかである。
浜岡原子力発電所の3号機,4号機の格納容器はマークⅠ型といわれる型式のものである。このマークⅠ型格納容器には次の2つの大きな問題がある。
第1 格納容器の体積が小さすぎるので,ひとたび炉心損傷にまで進展するような過酷事故が起きると,格納容器の圧力が異常に高くなってしまうこと
第2 設計において下記(ア)及び(イ)の「水力学的動荷重」の問題が全く考慮されていないこと
記
(ア)原子炉圧力が崩壊熱によって運転圧力より高くなると,原子炉の破損をふせぐためにSRV(逃がし弁)が自動(または手動)で開き,その弁から大量の水蒸気が排気管に噴出し,最終的に圧力抑制プールに流入するが,その際,圧力制御室は排気管の先端から勢いよく吹き出す水蒸気の強烈な力を受ける。
(イ)管破断によるLOCA(冷却材喪失事故)が起きると,破断箇所から秒速1000mにも達するような高速の大量の高温高圧の水蒸気が一気にドライウエルに噴出するが,この水蒸気によって格納容器を満たしていた大量の水に溶けない窒素ガスが圧縮され,ベント管,ベントヘッダー,ダウンカマーを経て圧力抑制プールへの押し込まれ,押し込まれた瞬間に一気に膨張し,プールを激しく膨張,動揺させ,それによって圧力抑制室に大きな力を加える。
更にマークⅠ型格納容器は,地震によるスロッシング(圧力抑制室の水面の動揺)が設計基準に取り込まれていないという問題がある。
即ち,スロッシングによりダウンカマー先端が圧力抑制室のプール水面から露出し,蒸気が圧力抑制室の気中部に吹き出してしまい,蒸気凝縮ができなくなり,その結果,圧力抑制室の圧力抑制機能が失われる可能性がある。
また,スロッシングで圧力抑制プールが大揺れすると,圧力抑制室にスロシング荷重が作用し(場合によっては,水力学的動荷重が量重し),圧力抑制室を破壊してしまうという可能性もある。
使用済みの核燃料は,定期点検で取り出したものも含めて,原子炉建屋の上方にあるプールにおいて水中保管されている。原子炉のように格納容器で覆われているわけではない。使用済み燃料は,水で冷やし続けなければ,崩壊熱で,燃料棒が破損し,メルトダウンを起こし,大量の放射性物質をまき散らす危険性がある。福島第1原発4号機ではその恐怖が現実化する一歩手前までいった。
強い地震動でプールが破損したり,長周期の揺れでスロッシング現象を起こし,巨大な水圧がかかった場合にプールが破損する可能性がある。プールが破損して水がなくなってしまえば,メルトダウンに至る。
(1)地震国日本に原発はつくるべきではない
① 日本列島を形づくったプレートの動きは,今でも続いているため,日本は世界でも有数の地震国となっている。
例えば,マグニチュード7.0以上の地震は世界中でこの90年間に900回ほど起きているが,そのうちの10パーセントもの地震が,付近の海を入れても面積では世界の1パーセントしかない日本で起きている。つまり,世界の平均の10倍もの地震が,日本で起きているのである。
また,マグニチュード8.0を超える巨大地震も,日本はその面積に比して多く発生している。1940年から現在までの約半世紀の間に世界でマグニチュード8.0を超える地震は51回起きているが,千島列島南部や台湾東部沖の地震も含めると,そのうちの7つ,つまり14パーセントもが日本周辺で起きているのである。
② 下記地図は,マサチューセッツ工科大学「MIT NSE Nuclear Information Hub:Nuclear Plant Siting and Earthquake Risk」に掲載されている地震と原発の立地場所に関する分析結果である。 (http://mitnse.com/2011/05/04/nuclear-plant-siting-and-earthquake-risk/)
緑色の斑点は世界にある222の商業用原子力発電所を表している。赤い斑点は1973年から2010年までに発生したマグニチュード7.0以上の地震(520回発生)を表している。この図から,原子力発電所を表す緑色の斑点が目立つヨーロッパでは,地震を表す赤い斑点はみられず,また,米東海岸も同様であることがわかる。世界の原子力発電所の圧倒的多数は大規模地震のリスクが低い地域に建設されており,大規模地震のリスクの高い地域には原子力発電所は建設されていないのである。つまり,地震大国の中で日本だけが唯一の原発大国でもあるのである。
③ そもそも,原子力技術は,上記図からも明らかなとおり,アメリカやヨーロッパなど,ほとんど地震のない国々で生まれたものである。その原子力技術が地震大国日本に輸入され,現在,日本には,17か所の商業用原子力発電所があり,54基の発電用原子炉が稼働している(停止中のものを含む。2011年5月末現在。)。
日本が導入した米国式の原子力発電所は,もともとは地震を想定してつくられたものではない。そのような,技術を地震大国である日本に取り込むことの危険性は,福島第一原発事故の例からも十分明らかとなっている。
地震大国である日本に原子力発電所はあってはならないのである。
(2)基準地震動Ssは予想される最大の地震動となっているか。
① 被告は,1978年に原子力安全委員会が策定した「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(旧指針)に基づいて,基準地震動S1,S2を策定し,それを用いて地震応答解析を実施し,各施設の発生応力値が許容値を上回っていないことを確認したと主張するが,旧指針は不十分だということで,2006年9月に大幅改訂された(新指針)。したがって,旧指針をクリアしていることは浜岡原発の耐震性を何ら保証するものではない。
被告は,改訂された新指針に基づいて,新たに基準地震動Ssを策定し,それに基づいて,3,4号機について原子炉建屋基礎地盤の安定性評価,耐震設計上重要な構築物及び機器配管の耐震安全性評価,屋外重要土木構造物の耐震安全性評価並びに地震随伴現象に関する評価を実施し,その結果,耐震安全性が確保されていることを確認し,その評価内容については原子力安全・保安院に報告書を提出し,5号機についても同様にして,同院に中間報告を提出していると主張する。しかし,原子力安全・保安院の審査(バックチェック)は終了しておらず,浜岡原発が新指針をクリアしているかどうかさえ,現時点では不明である。 したがって,被告の主張するところは,浜岡原発の耐震安全性については,何ら証明するものではない。
② ところで,新指針に基づいて,電力各社は,Ssを策定し直したが,東京電力柏崎刈羽原発では旧指針のS2が450ガルだったのが,1ないし4号機については,Ssは2300ガルに引き上げられ,突出した大きなSsとなっている。その他の原発は,450ないし800ガルである。これは中越沖地震で解放基盤表面で1699ガルだったことが明らかになったからであろう。
浜岡原発は,S2は600ガルだったがSsは800ガルとされている。被告は,A及びAsクラス(新指針ではSクラス)構築物や機器・配管等については1000ガルにも耐えられるように耐震裕度向上工事を施したという。しかし,柏崎刈羽原発で観測された1699ガルという地震動は浜岡原発の地下では絶対に生じないと言えるであろうか。
福島第一原発では,Ssは600ガルと策定され,それについての原子力安全・保安院のバックチェックも終わっていたが,東日本太平洋沖地震で,2号機,3号機,5号機でSsに対する最大応答加速度を上回る加速度が観測されており,Ssの策定方法,それに対する原子力・安全保安院の審査が不十分であったことを示している。
原発事故は万が一にも起こってはならないものであるから,どのような地震動にも耐えられるものでなくてはならない。
しかるに,新指針そのものが「残余のリスク」なるものを認めて,不完全であることを認めているのである。福島第一原発の事故は,「残余のリスク」が現実化したものと言えよう。
いずれにしても,新指針そのものの改訂は不可欠である。浜岡原発を襲うであろう地震も最大クラスの地震を想定しなければならない。
中央防災会議の2011年9月28日付け「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告」は,「これまでの地震・津波の想定結果が,実際に起きた地震・津波と大きくかけ離れていたことを真摯に受け止め,今後の地震・津波の想定の考え方を抜本的に見直さなければならない」とし,それまでの地震の想定の仕方そのものに誤りがあったことを認めた。それまでの地震の規模の想定の仕方は,「過去数百年間に経験してきた最大級の地震のうち切迫性の高いと考えられる地震を対象に,これまで記録されている震度と津波高などを再現することのできる震源モデルを考え,これを次に起きる最大級の地震として想定」するというものであった。しかし,「その結果,過去に発生した可能性のある地震であっても,震度と津波高などを再現できなかった地震は地震発生の確度が低いものとみなし,想定の対象外にしてきた。」のである。
さらに内閣府は2011年8月に「南海トラフの巨大地震モデル検討会 中間とりまとめ」を公表したが(想定される東海大地震も南海トラフの巨大地震に含まれる),そこでも「これまで中央防災会議が対象としてきた南海トラフで発生する大規模地震の想定は,過去に発生した地震と同様な地震に対して備えることを基本として,過去数百年間に発生した地震の記録の再現を念頭としてきた。」とそれまでの地震の想定の仕方を総括し,そのような方法からの脱却が必要なことが述べられている。そして,南海トラフにおける最大の地震の「検討に当たっては,南海トラフで発生した過去の地震の特徴やフィリピン海プレートの構造等に関する特徴などの現時点の科学的知見に基づきあらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波を検討する必要がある。」としている。
被告の地震想定の仕方は,国の機関においても,真摯に反省し,克服されなければならないとされている古い,間違った地震想定の仕方に依拠しており,根本的な見直しが必要である。
(3)耐震上の余裕について
① 原発における安全審査は,各機器,配管に対する発生応力値を算定し,それが許容値の範囲内におさまっているか否かによってなされる。
よって,発生応力値が許容値に比べて値が小さい場合,この許容値と発生応力値の差が本来の意味の安全余裕である。
しかし,被告は,本原子力発電所は安全余裕として,①発生応力値の算定(解析)における余裕,②発生応力値が許容値に対して有する余裕,③許容値の設定における余裕という3つの耐震上の余裕を有していると主張している(被告準備書面(1)47頁以下)。
上記3つの余裕のうち,①及び③の余裕というのはありもしない余裕であり,安全審査のうえで考慮すべきではない。
ここで許容値とは,材料がその使用環境下で性能を発揮できる限界の応力値のことを材料の基準強さと呼べば,許容値とは基準強さそのものではなく,基準強さを安全率で割った値である。
②発生応力値の算定における余裕の問題
ここで発生応力値の算定における余裕とは,具体的耐震設計に用いている発生応力値が,設計に用いた地震が実際に生じた場合に発生する真の発生応力値より大きなものとなっていることによって生じる余裕とされている。
具体的設計に用いられている発生応力値は,基準地震動S1,S2(旧指針の場合)によって原発の重要構造物にどのような応力が発生するかということで算定されている。
その場合には,算定される応力が「実際の地震動のよって発生する応力」より「大きめに算定」されなければ「余裕」があることにはならない。
真の応力というものは,実際に発生するまでは算定することは不可能であり,不明な真の応力と算定応力を比較することには無意味なことである。
実際に発生する応力が,理論的に算定される応力を常に下回るという保証もどこにもない。
現に2005年8月の宮城県南部地震(M7.2)で,東北電力女川原発がS2を上回る地震動で揺れ,2007年3月には能登半島地震(M6.9)で北陸電力志賀原発が同様にS2を超える地震動に見舞われた。
2007年の新潟県中越沖地震(M6.8)でも柏崎刈羽原発でも基準地震動S2を大幅に超える揺れが発生したのである。
また,設計用減衰定数(地震などの揺れに対して構造物は徐々に揺れが小さくなっていくように減衰性能を有している。減衰定数は減衰の程度をさす定数のことである。減衰が小さいほど地震による揺れは大きくなる)を実際より小さめに見積もることによる余裕もあるとされるが,それもなんらの耐震上の余裕とはならない。
実機の配管の減衰定数自体がどういう値か不明であるために,その値が実験に用いられたデータの下限値をさらに下回る可能性があることから,被告が主張するように実験により得られたデータよりも相当に安全側の数値を使用しているとしても,それは余裕を示すものではない。
③ 許容値の設定における余裕の問題
本件原子力発電所の構築物及び機器,配管の具体的耐震設計において用いた許容値は,構築物及び機器,配管の破壊に至るまでに大きな余裕を有しているとされる。
ただこうした余裕も,基準地震動S2に対する許容値が余裕を持って設定されているということでしかない。
前述のように余裕があるかどうかは基準地震動S2次第であり,現実にS2を超える応力を発生させる地震が発生しない保証はまったくない以上余裕があることにはならない。
また,許容値についてすでに説明した通り,基準強さを安全率で割った値である。つまり,安全率とは基準強さを許容値で割ったものである。
許容値に余裕を持って設定するということは,安全率を大きくとるということである。
安全率は1より大きな値をとることになるが,安全率が大きいということは,応力予測の不確実性が大きいということである。
原発では,構造物の複雑性や熱荷重,地震荷重等の不確実な設計荷重,使用する材料の劣化や加工上の誤差等材料自体の不確実性等不確定要素が無数に存在するのであるから,安全率を大きめにとらなければならない。
安全率を大きめにとることは,不確実な要素を吸収するために見かけの余裕であり,工学的に必要不可欠な安全代である。
それは,決して安全余裕ではない。
(4)制御棒挿入失敗の可能性
沸騰水型原発は加圧水型原発と比較して,制御系に大きな弱点を抱えている。すなわち,圧力容器の下部に制御棒駆動系と計装装置が密集しており,制御棒は重力に逆らって下から上に挿入しなければならないからである。過去にも各地の原発で制御棒の脱落・誤挿入事故が15件も起き,うち1978年11月2日の福島第1原発3号機と1999年6月の志賀原発1号機の事故では臨界に達していたにもかかわらず,長期間にわたり隠蔽されていたことがある。浜岡原発3号機でも1991年5月31日に制御棒3本が脱落する事故があった。
地震が発生した場合,原子炉建屋の地下に設置した地震感知器が120ガル以上の揺れを感知すると自動的に制御棒駆動機構が作動し,制御棒が挿入されることになっている。
福島の場合,震源が原発から遠かったため,速度の速い縦揺れ(P波)の方が主要動である横揺れ(S波)よりもかなり早く到達したため,大きく揺れる前に制御棒が挿入され,原子炉が停止したものと思われる。
しかし,浜岡原発の場合,地震の震源は原発の直下とされており,縦揺れが来てから横揺れが襲来するまでの時間はごく短い。したがって,制御棒が挿入される前に激しい横揺れにおそわれ,制御棒が挿入できない可能性は福島原発の場合に比べて格段に高い。
(5)津波
① 津波が発生する仕組み
太平洋沖や駿河湾の海底下で地震が発生した場合,本件原子力発電所がある御前崎付近に津波が押し寄せる。その仕組みは以下の通りである。
太平洋沖の場合水深は,6000m,最深では9000mに及び,海底は数百気圧の水の力を受けている。地震の発生する深さでは,海底面下の岩石の重さの分の圧力も受けているので,数千気圧以上の膨大な力を受けている。岩石に上下・左右・前後から等しく大きな力を加えても破壊することはない。一方,岩石にずれるような力が加わると破壊(剪断破壊)が起きる。岩石がずれるような力によって破壊する現象が地震である。剪断破壊によって生じた面(破壊面)が断層面である。加えられていたずれの力(剪断応力)が解放されると,その結果として破壊面の周辺に力が加わり,周辺の岩石を変形させ,地震の波(地震波)を放出させる。つまり,地震とは,岩石がずれるように破壊され,地下に断層(震源断層)が形成される物理現象である。地震波が地表に到達すると,地面が上下・水平に震動する。この揺れを地震動という。海底の地震動が海水に伝わると,海水も地震動に連動して上下し,波となって広がっていく。この波が陸に押し寄せて津波となる。
津波の速度は,水深が深いほど速く,水深が浅いほど遅くなる。水深が浅くなるほど後ろの波が前の波に追いつき重なって,津波の高さが高くなる。
② 津波の様々な値
津波の規模を表す値には様々なものがある。以下,多く使われるものについて定義を示す。
「津波の高さ」とは,押し寄せた海水の海岸線における高さであり,津波がないときの潮位(平常潮位)と津波によって海面が上昇したときの高さとの差をいう。
「浸水高」とは,平常潮位と津波によって建物などが水につかった部分までの高さとの差をいう。
「遡上高」とは,平常潮位と津波が陸地を駆け上がった(遡上した)地点の高さとの差をいう。
③ 津波による浸水被害
ア 「最大クラスの津波」を想定すべきである
被告は,準備書面(1)において,敷地前面における最高水位(遡上高)はT.P.+5.8m程度,敷地付近に想定する必要のある水位上昇は,最大T.P.+6.0m程度であるとする(ただし,被告ホームページ中には,T.P.+8m程度と想定している旨の記載がある。)。そして,かかる想定を前提とした上で,津波による水位上昇に対しては「砂丘堤防が存在すること及び原子力発電所の原子炉建屋及び海水熱交換器建屋の出入り口に腰部防水構造扉等を設置していることを理由に,「余裕をみた水位上昇に対しても本件原子力発電所の安全確保に支障がないことを確認した」と主張する。
しかし,被告が想定している津波は,防波堤など海岸保全施設等の建設を行う上で想定する津波である。原子力発電所の津波対策としては,このような想定では足りない。
中央防災会議は,「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告」(2011年9月28日)の中で,想定すべき津波には二つのレベルがあるとして,以下のように述べる。
「今後の津波対策を構築するにあたっては,基本的に二つのレベルの津波を想定する必要がある。一つは,住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で想定する津波である。超長期にわたる津波堆積物調査や地殻変動の観測等をもとにして設定され,発生頻度は極めて低いものの,発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波である。今回の東北地方太平洋沖地震による津波はこれに相当すると考えられる。もう一つは,防波堤など構造物によって津波の内陸への浸入を防ぐ海岸保全施設等の建設を行う上で想定する津波である。最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く,津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波である。」(9頁)
さらに,同報告は,「最大クラスの津波高への対策の考え方」として,「今回の巨大な津波の発生とその甚大な被害から,海岸保全施設等に過度に依存した防災対策には問題があったことが露呈した」ことから,「東北地方太平洋沖地震による津波や最大クラスの津波を想定した津波対策を構築し,住民等の生命を守ることを最優先として,どのような災害であっても行政機能,病院等の最低限必要十分な社会経済機能を維持することが必要である。」とした上で,原子力発電所などの施設が被災した場合,「その影響が極めて甚大であることから,これらの重要施設における津波対策については,特に万全を期すよう考えていくことが必要である」とする。
しかし,被告が想定しているのは,中央防災会議が上記報告の中で述べる「二つのレベル」の津波のうち,「防波堤など構造物によって津波の内陸への浸入を防ぐ海岸保全施設等の建設を行う上で想定する津波」のみであり,中央防災会議が想定すべきである,とする「最大クラスの津波」ではない。
イ 被告の想定する津波を前提としても浸水のおそれは大 。大きい。
原子力安全・保安院や被告が想定している程度の浸水高(T.P.+15m)でも,砂丘及び被告が設置予定であるという防波壁は,浸水被害の防止策として不十分である。
福島第一原発の原子炉建屋,タービン建屋等の海側の敷地の浸水高がO.P.(O.P.:小名浜港工事基準面)約+14~15mであり(原子力災害対策本部「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書」-東京電力福島原子力発電所の事故について-),原子力安全・保安院は,2011年5月6日付ニュースリリースの中で,「福島第一事故を踏まえ考慮想定すべき浸水高さ」をT.P.+15mとしている。
そして,被告は,本件原子力発電所の「敷地は,T.P.+6.0ないし8.0mに整地され,敷地前面には幅約60ないし80m,高さT.P.+10ないし15mの砂丘堤防が存在する」こと(被告準備書面(1)51頁)及び敷地の海側に高さT.P.+18mの防波壁を設置する予定であること(「浜岡原子力発電所における津波対策について」(被告ホームページ)中の「津波対策の概要」)から,安全性に問題はないとしている。
しかし,単に津波よりも高い壁を作るだけでは,浸水対策としては不十分である。
すなわち,津波は「4mの高い波」ではなく,「4mの水面の高さをもつ早い流れ」であるから,津波は護岸や防波堤にぶつかった瞬間,前進できなくなって水の運動が停止し,海面が盛り上がって,理論的には衝突前の1.5倍くらいの高さになる(河田恵昭「津波災害」17頁)。また,津波は10kmもの長波長であり,後ろから押し寄せる波によってまた高く盛り上がる。
また,津波自体の破壊力によって防波壁が破壊され,敷地・建屋が浸水するおそれがある。すなわち,進行中の高速で大量の海水の前進が突然ストップさせられるので,衝撃的な圧力が働き,そのために防波壁が破損する可能性がある(河田恵昭「津波災害」17頁)。
このように,たとえ被告が想定する程度の津波が襲った場合においても,依然として浸水の危険性が高い。
ウ 浜岡原子力発電所付近の海底地形
東京大学地震研究所の都司嘉宣准教授の分析によれば,本件原子力発電所付近の御前崎の海底地形は,東日本大震災の際,首都圏で唯一津波による死者が出た千葉県旭市飯岡地区沿岸の海底地形とよく似ている。
御前崎近くの海底地形は,岬付近の海底だけが遠浅で沖に突き出す形となっており,その周縁が急激に深くなっている。海底の浅い部分が沖に突き出ていることによって,岬の突端に向かって波が集中し津波の高さが急激に増すことが考えられる(アットエス〔静岡新聞〕2012年1月8日)。
このような御前崎の海底地形の特徴に鑑みても,浜岡原子力発電所が津波の被害に遭う可能性は高いといえる。
④ 冷却用海水が取水不可能となるおそれ
津波が押し寄せ,それが退いた際には水位の低下が予想される。これにより取水できなくなる危険が大きい。 被告は,津波による水位低下について,「津波による最低海位が取水口の下端レベルを4分間程度下回る可能性があるが,冷却に必要な海水が取水槽に20分間以上確保される設計であることから,本件原子力発電所の安全確保に支障がない」と主張する。(被告準備書面(1)51頁)。
しかし,津波の運んでくる砂,瓦礫などにより取水口が塞がれる可能性がある。
押し寄せた津波によって全交流電源喪失という事態になり,さらに砂や瓦礫によって取水口が塞がれた場合,果たしてわずか20分間の間に取水機能を復活させることができるのか,取水槽にたまっている海水でその間の冷却を賄えるのかという点については何ら検討されていない。
(6)地震時地殻変動
現在の原子力発電所の耐震設計審査指針では,現在においても設計時に地震時地殻変動については考慮することとされてはいない。
しかし,地震随伴事象として地震時地殻変動はきわめて重要である。
① 地震時地殻変動とは
地震は,地下の弱面系(大小の断層,亀裂,割れ目システム)の両側の岩体が,造構力による変形を解消するように逆向きにずれ動くことで発生する。こうした地下の岩盤破壊を震源断層運動という。
震源断層運動が地表の浅い部分まで達すると地表の広範な範囲が横に動いたり,上下に隆起,沈降することがある。これ地震時地殻変動という。
岩体のずれは,断層面に近いところほど大きく,離れるにつれて小さくなる。浅い大地震の震源域付近の地表は,震源断層面の形状やずれ方に応じて大きく隆起,沈降することになる。
② 地震時地殻変動の影響
地殻変動が生じると,ずれの量は断層面上で不均一(アスペリティの存在)だから表面の変形は凹凸して,原発敷地程度の広がりにおいても無視できない傾斜を生じることもある。さらに基盤の地殻変動による敷地地盤の変形や破壊もあり得る。
③ 現実に地震で大きく隆起した地盤もある
プレート間の大地震であった1854年の安政東海地震の際には,富士川河口付近から天竜川河口付近までの海岸が,場所によっては1~3メートル隆起した。
2007年7月の新潟県中越沖地震により,柏崎刈羽原発の敷地でも不均等に隆起する部分と沈降する部分が発生した。その結果,原発建屋に傾きが発生し,多くの建物,構築物が損傷した。
④ 海底隆起により取水不可能となる可能性がある
東日本大震災により,東北地方太平洋側の震源近傍の海底が,7メートルから10メートル隆起したことが明らかとなった(独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)2011年12月2日付プレスリリース)。東海地震の場合は震源域が直下にあるため,東北地方太平洋沖地震と同様の事態が発生した場合には、浜岡原発の位置する地盤が7~10メートル隆起する可能性がある。
仮に,東日本大震災と同様に7メートル隆起した場合,取水口が海面より上に出てしまい,取水できなくなるおそれがある。
(7)地震学と防災のあり方
① そもそも地震「予知」は可能なのか
ア 地震学とは,地震の発生機構及びそれに伴う諸事象を解明する学問をいう。地震予知,すなわち,地震が「いつ」,「どこで」,「どのくらいの大きさ」で発生するかを地震の発生前に精度よく予測することができれば,地震による災害を最小限にとどめることができることから,地震学には,地震予知が期待されているといえる。しかし,地震予知は果たして可能なのだろうか。
1978年に成立した大規模地震対策特別措置法は,「地震は予知できる」ことを前提に制定された法律である。この当時,地震学者の多くは前兆を捕まえれば地震予知ができると考えていた。
イ しかし,地震というのは,大まかに説明するならば,相互に固着している岩盤に力が加わってひずみが生じ,このひずみが限界を超えた時に,固着していた岩盤が壊れることによって発生するところ,ひずみの限界がいつ到来するかを正確に予測することは,現代の科学では不可能である。
地震学によって阪神・淡路大震災を予知することができなかったことから,地震が「いつ」発生するかを予知することはできないという前提のもと,地震発生の長期予測を行うこととなった。これがいわゆる「長期評価」である。文部科学省の地震調査研究推進本部から公表され,毎年更新されている。
この「長期評価」は,「いつ」を予測できないために導入された。つまり,地震予知の要素のうち,他の二つ,「どこで」と「どのくらいの大きさ」についてはある程度わかっていることを前提としている。
ウ では,上記長期評価によって,2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は想定されていたのであろうか。
この点,東北地方の太平洋沖に関し,上記「長期評価」では,「どこで」については,三陸沖から房総沖の海溝寄り・三陸沖北部・三陸沖中部・宮城県沖・三陸沖南部海溝寄り・福島県沖・茨城県沖の7つの対象地域が想定され,「どのくらいの大きさ」については,それぞれの領域にマグニチュード6.7から8.2までの規模が予測されていた。なお,宮城県沖地震については単独で起きる場合と,連動して起きる場合の2パターンが想定されていた。
しかし,実際に発生した東北地方太平洋沖地震は,三陸沖中部から茨城県沖の陸側と海溝側にわたる巨大な震源域で断層運動を起こした,マグニチュード9.0の地震であった。宮城県沖約130㎞にある破壊開始点から断層すべりが始まり,それが秒速1~2㎞で震源域に広がった。上記「長期評価」で想定された,小さな6つの領域での個別の地震ではなく,地震の規模も,上記「長期評価」が想定した最大マグニチュード8.2をはるかに上回るものであった。
つまり,東北地方太平洋沖地震は,その場所も規模も全く想定できていなかったのである。すなわち,上記「長期評価」を業務とする地震調査研究推進本部の地震調査委員会は,地震当日,「宮城県沖・その東の三陸沖南部海溝寄りから南の茨城県沖まで個別の領域については地震動や津波について評価していたが,これらすべての領域が連動して発生する地震については想定外であった」という評価を公表した。また,地震予知を業務とする気象庁も,同日,「三陸沖でこれほどの地震が起こるとは想定していなかった」と述べた。
エ 東北地方太平洋沖地震が全く想定されていなかったことは,福島原子力発電所事故対策本部が以下の驚くべき発表を行ったことからもわかる。すなわち,同対策本部は,2011年5月10日,「国内の原発で30年以内に震度6強以上の地震が起きる確率」について,具体的な数字を公表した。この数字は,2011年1月1日を基準に算定したものであるが,なんと,女川原発が8.3%,福島第一原発が0.0%,福島第二原発が0.6%,東海第二原発が2.4%であった。東北地方太平洋沖地震で甚大な被害が発生した福島第一原発の確率が0.0%というのだから,今般の東北地方太平洋沖地震が全く想定されていなかったことは明らかである。
② 予測できない地震が起こることを念頭に置くべき
ア いわゆるプレート境界型地震の場合,過去に発生した大地震にはそれぞれ縄張りのようなものがあり,それぞれの縄張りの中で大地震を繰り返してきたと言われてきた。
そのため,東北地方の太平洋沖の地震に関する上記「長期評価」も,区分けされた7つの地域において,それぞれ単独で地震が発生し,各地域に発生した地震が連動しないという前提で地震の想定が行われていた。
しかし,今般の東北地方太平洋沖地震は,そのような想定が覆され,区分けされた6つの地域に連動して地震が発生し,大地震となった。
イ 発生する可能性が高いといわれている東海地震についても,静岡県地域に単独で発生するのではなく,東北地方太平洋沖地震と同様,静岡県沖から高知県沖まで連動して発生する可能性が指摘されている。
すなわち,静岡県地域に東海地震が発生するとされる理由は,1944年に発生した東南海地震,及び,1946年に発生した南海地震の震源域が,安政年間の1854年に発生した大地震の震源域よりも狭かったことにある。残された静岡県地域にエネルギーが解放されずに蓄積されているというのである。
しかし,安政年間の大地震から既に158年,東南海地震から68年が経過しようとしているが,東海地震は未だ発生していない。
ところで,静岡県沖から高知県沖まで地震が連動して発生したことはそれ以前にもあり,宝永年間の1707年の大地震は静岡県沖から高知県沖まで地震が連動して発生している。
だとするならば,東海地震単独で発生するのではなく,静岡県沖から高知県沖までの地域で地震が連動して発生し,超巨大地震となる可能性は十分にあると考えられる。実際に6つの区域で連動して東北地方太平洋沖地震が発生し,福島第一原発に甚大な被害を発生させている以上,このような超巨大地震発生の可能性を考慮する必要がある。
ウ また,東海地震については,以下の指摘もなされている。すなわち,「科学」2007年11月号で,田中三彦氏は次のように述べる。『(2007年)8月末から9月はじめにかけて神戸大学で開催された「日本第四紀学会」で,注目すべき研究が報告された。産業総合技術研究所・活断層センターの藤原治研究員,北海道大学大学院地球環境科学研究院の平川一臣教授ら5人からなる研究グループは,浜岡原発の東約2キロをボーリング調査した結果,「段丘を離水させる大きな隆起を伴った地震」が過去5000年の間に少なくとも3回(2800B.C.前後,1800~2000B.C.頃,400B.C.前後)起きた可能性が高いことを明らかにした。論文では,その3回の「あと」については明言していないが,「御前崎周辺の地層には大きな隆起を伴う1000年前後の間隔の地震と,より短い間隔の地震が記録されている可能性が高い」としている。浜岡原発にとっては非常に深刻な話だ。近い将来起こるとされる地震がじつは想定東海地震ではなく,この1000年周期の「超・東海地震」である可能性も出てきたからだ』。
浜岡原発近辺で上記のような大きな隆起を伴う地震が発生すれば,原発に甚大な被害が生じることは必定である。過去少なくとも3回発生した事実がある以上,このような地震発生の可能性を考慮する必要がある。
エ また,浜岡原発近辺で内陸直下型地震が発生する可能性も考慮すべきである。
日本は過去たびたび内陸直下型地震に襲われ,甚大な被害が発生している。阪神・淡路大震災は近年最悪の被害を発生させた内陸直下型地震である。しかし,なぜ,この地域に直下型地震が襲ったのか,現在の学問では不明とされている。
浜岡原発近辺で内陸直下型地震が発生すれば,原発に甚大な被害が生じることは必定である。だとするならば,浜岡原発近辺で内陸直下型地震が発生する可能性も考慮する必要がある。
この点,原発は活断層のうえに立地しないから浜岡原発近辺で直下型の大地震は起こらないという見解もある。ここで活断層というのは,大地震の際の地表のずれが最近の地質時代に何度も同じ向きに生じて累積し,地形や地層のずれとして線状に認められるものをいう。
しかし,大地震の震源断層面が深くて岩石のずれが地表に現れなかったり,大地震がまれにしか起こらなくて地表のずれが浸食されて累積しなかったりすれば,地下に大地震発生源があっても活断層はできない,つまり,活断層がなくても直下の大地震は起こるのである。現に,1927年北丹後地震(マグニチュード7.3),1943年鳥取地震(マグニチュード7.
2)1948年福井地震(マグニチュード7.1)などは,いずれも地表地震断層を伴う海岸近くの直下型地震だが,活断層が認識できないところで発生した。
オ 要するに,予測不可能な大地震が浜岡原発を襲う可能性は十分にあるのだから,浜岡原発の安全性を検討するに当たっては,そのことを考慮しなければならないのである。
この点,2006年9月に制定された「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」では,地震学的見地からは,策定された地震動を上回る強さの地震動が生起する可能性は否定できないとし,耐震設計用の地震動の策定において,「残余のリスク」が存在することを認め,この「残余のリスク」の存在を十分認識しつつ,それを合理的に実行可能な限り小さくするための努力が払われるべきであるとした。つまり,予測不可能な大地震が原発を襲う可能性を正面から認めたのである。
しかし,福島第一原発の原発震災がもたらした,とりかえしのつかない甚大な被害を目の当たりにした今日,「残余のリスク」が少しでも残っている限り,原子力発電所を稼働させるべきではない,まして,浜岡原発は,上記のように,予測できない大地震発生の可能性が十分にあるのだから,浜岡原発において,残余のリスクを「合理的に実行可能な限り小さくするための努力」とは,原発の稼働を永久に停止すること以外にない。
③ 福島第一原発が地震により配管等が損傷した可能性
ところで,2011年6月1日に公表された「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書/東京電力福島原子力発電所の事故について」では,地震による被害が外部電源喪失に限られるかのような記載が見られる。すなわち,「今回の地震において,福島第一原子力発電所の原子炉建屋基礎盤上で観測された地震動の加速度応答スペクトルは,耐震設計審査指針に基づく基準地震動による応答スペクトルを一部で超えていたことが確認されている。ただし,現在のところ,地震による被害は外部電源系に係るものである・・」とされ,あたかも,原発の機器・配管類は地震による影響を受けなかったかのような記載となっている。しかし,このような記載は事実を歪めるものであり,不当というべきである。
東北地方太平洋沖地震の地震動は,建物を壊しにくい短周期(1秒間の振動回数が多い)が強かったと言われているが,原発の機器・配管類は一般に短周期に弱い。それとともに,東北地方太平洋沖地震の地震動の継続時間が想定よりはるかに長かったことは,設備・機器の損傷をもたらす方向に働いたと思われる。基準地震動Ssの強い揺れの時間はせいぜい30秒程度だが,東北地方太平洋沖地震の本震の強い揺れは130秒くらい,とくに激しい部分だけでも約60秒もあった。これは,繰り返し荷重として構造物に激しく作用する。原発の機器・配管類が地震による影響を受けなかったと考えるのは不合理である。
地震による原子炉系配管類の損傷の可能性を指摘するものとして次のものがある。
岩波書店・科学11年9月号,田中三彦「東電シミュレーション解析批判と地震動による冷却材喪失事故の可能性の検討」
エントロピー学会編「原発廃炉に向けて」(日本評論社)
井野博満「福島原発で何が起こったか-原因と意味」
後藤政志「福島原発で何が起こったか-原発設計技術者の視点」
(1)基盤岩
本件原子力発電所の基盤岩は,かつて約600万年前の地層とされていたが,最近の詳しい地質調査(地質調査所,1988年)の結果,相良層群より一時代新しい掛川層群下部層(新第三紀鮮新世前期)に相当する比木互層(約400万年前。以下「相良層群比木互層」という。)であることが判明した。そして,この相良層群比木互層は,砂岩の厚さが5~10センチメートルであるのに対して,泥岩の厚さが10~20センチメートルを示す泥岩優勢の互層であるが,砂岩の固結度がとりわけ低い軟岩である(「地震と原子力発電所」藤井陽一郎・205頁参照)。
また,本件原子力発電所の「3号炉申請書には,ボーリング調査(孔数185本,掘削深度平均約23.65m,最大深度55.75m)に基づく,地質柱状図16葉が記載されているところ,これらのうち,たとえば原3ボーリングによる地質柱状図をみると,記事欄には『深度10.00~25.00mの砂岩はほとんど流失』となっており,泥岩部に比べ,砂岩部の固結度が著しく劣っていることが明白である。他の柱状図の記事欄にも『流失コアが多い』『砂岩の破砕されたコア』『砂岩はほとんど流失』『固結度が低く,ブラインド・ジョイントに富む』などの記述が見られ,岩盤良好度(R・Q・D)が50%を割っている不良岩盤が多く見受けられる。」(「原子力工業1982年1月号」3頁)とされている。このことからも,本件原子炉施設設置敷地の基礎岩盤の脆さがわかる。
以上のことから,相良層群比木互層は未固結であり,非常に脆い岩盤であることは明らかである。
(2)活断層・H断層
被告は,H断層系には少なくとも約8万年前以降における活動はなく,H断層系は地震を起こしたり,地震の際に付随して動いたりする断層ではなく,耐震設計上考慮すべき活断層ではないと主張する。
しかし,H断層系も耐震設計上考慮すべき断層である。
石橋克彦神戸大学名誉教授は,「活断層というのは,大地震(=地下の広大な震源断層面に沿う岩石のずれ破壊)の際の地表のずれ(地表地震断層)が最近の地質時代(研究者によって数十万~200万年間)に何度も同じ向きに生じて累積し,地形や地層のずれとして線状に認められるものである。したがって,顕著な活断層があれば,その地下に拡がる面で将来も大地震がおこる可能性があるのは確かである。しかし,大地震の震源断層面が深くて岩石のずれが地表に現れなかったり,大地震がまれにしかおこらなくて地表のずれが浸食されて累積しなかったりすれば,地下に大地震発生源があっても活断層はできない。つまり,活断層がなくても直下型の大地震がおこる」(「原発震災」・石橋克彦・721頁)と述べている。
例えば,2011年4月11日に,福島県いわき市を襲った震度6弱の地震の震源は「湯ノ岳断層」であるところ,同断層は従来,東京電力が,「活断層ではなく,原発耐震上の考慮は不要」と主張していたものである(「静岡新聞2012年2月2日朝刊」参照)。
また,伊藤通玄静岡大学名誉教授は、本件原発設置地域である「御前崎付近には北北東方向と北北西方向に走る一群の活断層が認められ,それらによって南西にゆるく傾斜する御前崎の台地面は分断され,場所によっては最大数m変化している。さらに,芹沢断層や広沢断層についてはそれを横切る段丘崖線が左ずれしているように見え,横ずれの可能性がある。したがって,およそ過去1万年以降は活動していないとされるH断層系も活断層である可能性は否定できず,予想される東海大地震の発生にあたってこれが二次的断層活動を行う可能性を考慮すべき」(「原子力工業1982年1月号」3頁、伊藤通玄「浜岡原子力発電所周辺の地質及び岩盤の性状」)と指摘している。
もともと、8万年動かなかったという被告の主張は、ひとつの見解にすぎないし、仮に8万年動かなかったとしても、今後も動かないという保証はない。平成18年に改訂された耐震設計審査指針によってもなお活断層の定義が緩く、活断層の評価期間が短すぎる。原発事故は万が一にも起こってはならない事故であるから、活断層についても広く定義すべきである。石橋克彦神戸大学名誉教授は、指針改定の際の分科会において「約50万年前以降の断層変位基準から0.01m/1000年以上の平均変位速度が推定される活断層は、基準地震動の発生源として考慮する」との案を提出していたが、その根拠は,米国では原発の安全停止地震を策定する場合に考慮すべき断層は地表付近で過去3万5000年間に少なくとも1回の変位(ズレ)か過去50万年間に繰り返しの変位を示すものと定められていること,日本列島の現在の変動は50万年前から連続していることにあるとしている。
したがって,約8万年活動していないとしても,H断層系が活断層であり,東海大地震が発生した際に二次的断層活動を行う可能性は否定できない。
仮にH断層が,活断層でないとしても,敷地の地盤の弱線となっていて,地震の際には,地震に伴ってずれ動いてしまう可能性も否定することはできない。
耐震設計は,こうした地盤が不均等に揺れ動かないことが大前提となっている。原子力発電所の建屋の基礎地盤が,不均一に揺れ動いてしまうなら,耐震設計の大前提が崩れてしまうこととなる。
よって,H断層系は,耐震設計上考慮すべき断層であることは明らかである。
(3)小括
以上のとおり,本件原子力発電所は,非常に脆く危険な地点に立地しており,さらに,地震発生時には地盤の急激な隆起・変形が予測されるのであるから,東海大地震には到底耐えることのできない状況にあることは明らかである。
本件各原子炉施設の運転が開始されたのは,3号機が1987年8月28日,4号機が1993年9月3日,5号機が2005年1月18日であり,特に3号機は24年が経過している。
「老朽化」とは,古くなって不具合が発生することを指す。原子炉施設の老朽化は,使用中に材料が受ける熱や力(応力),酸化などの化学変化などにより起こるが,主な原因は疲労と腐食であり,特有なものとして,中性子照射による脆化がある。
(1)SCC(応力腐食割れ)
① SCCの発生は不可避である
ア SCCとは何か
SCCとは,金属材料が応力(引っ張り応力あるいは残留応力)と腐食環境にさらされることにより特定の部位で生じ得る亀裂現象のことをいう。
SCCの形態としては,ステンレス鋼などに含まれる金属の結晶粒と結晶粒の境目(粒界)に沿って割れが進展するIGSCC(粒界型SCC)と結晶粒を貫通する形で割れが進展するTGSCC(粒内型SCC)とがある。また,ステンレス鋼に中性子が照射され,一定程度に達すると,SCCが発生しやすくなるが,これはIASCC(照射誘導型SCC)という。
イ SCCの発生
(ア)初期のSCC(鋭敏化によるSCC)
1974年以降,わが国や海外のBWRにおいて,SUS304ステンレス鋼(鉄にニッケルとクロムを添加したステンレス鋼で,BWRで広く使用されていた。)配管のうち,溶接部近傍においてき裂が確認されるようになったが,これはステンレス鋼に耐食性を持たせているクロムが溶接時に入熱によってステンレス鋼に含まれる炭素と結合し,クロム炭化物として析出するなどして,部分的なクロム欠乏部が生じ,耐食性が低下する(このような現象を「鋭敏化」という。)ことに起因するIGSCCであると確認された(以下,「鋭敏化SCC」という。)。
その後,ステンレス鋼の炭素含有量を0.03%以下に低減すると鋭敏化SCCが発生しないことが確認されたことから,炭素含有量を0.03%以下にしたSUS304Lステンレス鋼及びSUS316L材をはじめとする低炭素ステンレス鋼(以下,「L」材という。)が開発され,わが国でもBWRで広く用いられるようになった。
当時の知見として,事業者及びメーカーは,L材の採用によって,材料以外の改善を図らなくてもSCC対策としては十分であると認識していた。
(イ)L材のSCC
ところが,1994年以降,海外でL材のシュラウド溶接部におけるSCCの発生事例が報告されるようになり,わが国内でも,L材を使用したシュラウドについて,点検者からひび割れの兆候が指摘されるようになった。
そして,2002年8月29日に公表された東京電力の自主点検作業に係る不正などを契機として,全国のBWRにおいてシュラウド及び再循環配管を対象として点検が実施された結果,ひび割れの発生が確認された。
L材のシュラウドのひび割れは,中間部リング,下部リング,シュラウドサポートリング(以下,「リング部」という。)及び中間部リングと下部リングの間の中間部胴(以下,「胴部」という。)などの様々な部位において発生しており,ひび割れの形状も発生部位などにより異なっている。ひび割れは,リング部では主に溶接線に沿って全周にわたって断続的に発生しており,胴部では放射状またはY字型に局所的に発生している。2004年5月31日時点で,女川原子力発電所1,2号機のリング部,福島第一原子力発電所4号機の胴部,福島第二原子力発電所2,3,4号機の胴部,リング部及び溶接線部,柏崎刈羽原子力発電所1,2,3,5号機の胴部及びリング部,浜岡原子力発電所1,2,3,4号機の胴部,リング部,及び溶接線部,島根原子力発電所2号機の胴部にそれぞれひび割れが確認された。
再循環系配管におけるひび割れは,いずれも配管内面の溶接部近傍で発生しており,再循環系配管の全体に発生している。2004年5月31日時点で,女川原子力発電所1号機10ヶ所,福島第二原子力発電所1号機1ヶ所,同2号機6ヶ所,同3号機9ヶ所,同4号機11ヶ所,柏崎刈羽原子力発電所1号機26ヶ所,同2号機5ヶ所,同3号機3ヶ所,同4号機6ヶ所,同5号機9ヶ所,浜岡原子力発電所1号機2ヶ所,同3号機9ヶ所,同4号機6ヶ所,志賀原子力発電所1号機6ヶ所のひび割れ及びその兆候が確認された。
(ウ)本件原子炉施設のシュラウド及び再循環系配管で確認されたSCCについて
a 被告は,上記点検により,本件原子炉施設のシュラウド及び再循環系配管において,上記各ひび割れ及びその兆候が確認されたことから,2002年9月20日から3ヶ月間にわたり,1,2,3,4号機を停止した。
b 本件原子炉施設におけるSCCを原因とする漏えい事故
1988年9月17日,定期点検中の1号機において,圧力容器とインコアモニタハウジングとの接合部から漏えいが発見され,同部分にき裂が確認された。
原因調査の結果,当該部分が入熱が大きい条件で溶接され,ハウジング内表面における強い鋭敏化域が溶接ルート位置下方まで広がり,この部分の運転時の圧縮応力を合成しても,運転中の作用応力としては溶接ルート位置で大きな周方向の引張残留応力(材料を引っ張る方向に残留している応力のことをいう。)が残り,これが溶存酸素を含む高温水中に置かれたためIGSCCが発生したものと推定された。
その後,被告は,内面スリープ溶接と拡管の組合わせ工法によって当該ハウジングの対策を実施した。
2001年11月7日,1号機の余熱除去系配管の爆発事故が発生した。
同月9日,同月7日に発生した1号機の余熱除去系配管破断に伴う原因調査のため停止中の同号機において,点検中に制御棒駆動機構ハウジングに漏えいが発見され,同部分にき裂が確認された。その後,原子炉圧力容器と同ハウジングの溶接部にもき裂が確認された。
原因調査の結果,当該き裂は,IGSCCによるものと推定された。
その後,被告は,き裂が確認された部位の取り替えを実施した。
(エ)制御棒のSCC
a 福島第一原子力発電所における制御棒のひび割れ
2006年1月9日,同原子力発電所6号機の定期点検中に,ハフニウム型制御棒にひび割れらしきものが確認されたことから,同型の制御棒17本について外観試験が行われた結果,合計9本の制御棒のシース部(ハフニウムを包んでいる金属板)及びタイロッド部(シース,ハンドルなどを接続している構造部材)にひび割れが確認され,そのうち1本の制御棒に欠損部を含む破損が確認された。
その後,同年3月,同原子力発電所3号機でも,5本の制御棒からひび割れないし欠損が確認された。
b 原子力安全・保安院の指示
原子力安全・保安院は,上記福島第一原子力発電所6号機で確認された事象を受け,被告を含むBWRを設置する事業者に対し,2006年1月19日,ハフニウム板型制御棒の使用の有無の調査及び健全性確認(運転中の原子炉におけるハフニウム板型制御棒の動作試験及び至近の定期事業者検査における点検の実施など)を指示した。
続けて,同院は,同年2月3日,熱中性子照射量が4.0×10 n/ を超えた同型制御棒は全挿入位置とすることなどを指示した。
(オ)大飯原子力発電所3号機における深刻な応力腐食割れ(SCC)
a 2008年4月,関西電力大飯原子力発電所3号機「原子炉容器Aループ出口管台溶接部」(ノズル部)で,極めて深刻な応力腐食割れが発見された。当初は「傷の深さが評価できない非常に浅いもの」と発表されたが,傷は削ってもなくならず,結局20.3ミリメートルの深さがあることが分かった。当該場所の板厚は74.6ミリメートルであったから,27パーセントの板厚が失われていたことになるとともに,それが見過ごされたまま数年間運転が継続されてきたことになる。
このSCCの場所は,原子炉圧力容器のノズル部のセーフエンドと呼ばれる場所であるところ,大飯原子力発電所は加圧水型(PWR)であるが,本件原子炉(BWR)にもノズル部にセーフエンドが付いており,セーフエンドが圧力容器製造時に工場溶接されていることなど,基本的な構造はすべての原子力発電所に共通である。そして,セーフエンドを交換することは,圧力容器そのものに手を加えることであり,技術的に極めて困難である。
(カ)本件原子炉施設5号機における水素爆発事故
2008年11月5日,5号機の機体廃棄物処理系において水素濃度が異常上昇し,さらに同系統内の希ガスホールドアップ塔の温度が上昇したことから,同原子炉が手動停止された。その後,被告は,この事故の原因は推定でき対策も講じたとし,原子力安全・保安院もこの報告を認めた結果,同原子炉は同年12月27日に再稼働した。そころが,5号機の水素濃度が再び上昇し,同年12月30日に再び手動停止された。
なお,気体廃棄物処理系の基本的な原理・構造は,本件原子炉施設1号機ないし4号機においても共通である。しかも,同系統においては2007年7月1日に同じ5号機に同様の事象が確認されていたにも関わらず,被告は,これを報告していなかた。さらに,2007年11月30日,女川原子力発電所3号機及び2008年4月2日,志賀原子力発電所2号機でも,全く同じ事故が報告されている。
② 福島第一原子力発電所における事故
同原発事故において,何が起こったのか,現状では推測の域を出ない。しかし,津波到達前に地震で原子炉系配管が破断ないし破損していた可能性が指摘されている。同1号機では,原子炉圧力の緊急低下が報告されており,何らかの配管破断ないし破損が強く疑われる。すなわち,地震発生後6,7時間経過した時点で同1号機の水位が4.5メートルも低下しているところ,このような水位の低下は,配管の破断ないし破損が生じたためか主蒸気逃し弁が作動したためか、どちらかが原因と考えられるが,主蒸気逃し弁が作動した形跡がないことから配管の破断ないし破損が強く疑われているのである。大量の崩壊熱が発生していながら,同1号機では,同2,同3号機と異なり,圧力容器内の圧力が上昇しなかったのは,地震直後に原子炉系の配管が破断し,そこから圧力が抜けていたと考えるのが合理的である。
③ 被告のSCCに対する対応について
以上述べたように,現状では,原子炉施設において,SCCを原因とする配管,制御棒等のき裂等が発生すること自体は不可避であり,SCCの発生・詳細なメカニズムには未解明な部分があることから,SCCの発生を抜本的に抑止する対策を講じることもできない状況にある。
この点,被告は,平素からSCCの発生を想定した点検・検査を行い,シュラウドや再循環系配管等にひび割れを発見した場合,その進展速度を予測して,将来の健全性を確認しつつ引き続き運転を続け,あるいは適宜交換するという方法により原子炉施設の安全性を確保することは可能であると主張すると思われる。
しかし,そもそも原子炉施設の設計時には,将来ひび割れが発生することなど想定されていなかった。したがって,耐震設計にあたって,ひび割れの発生など考慮されている訳もなかった。そして,現実には,漏えいを引き起こすまでひび割れを発見できなかった事例が多数報告されているし,なによりも,現に今われわれの前で起こっている福島の惨状は,点検・検査によっても発見されないひび割れが存在する可能性を示唆するものである。ひび割れが発生すれば,機器・配管の耐震性を確実に弱めることは,論証の必要もないほど明らかである。そもそもの設計・建設時の想定を遙かに越える地震動が襲うことがほぼ確実に想定される本件原子炉施設を運転するなど,タイマーの壊れた時限爆弾のスイッチを入れるに等しい。
(2)配管の減肉現象
① 減肉とは
減肉とは,文字どおり「肉」厚が「減」少することをいう。肉厚の減少は,すなわち,金属材料が全体的に薄くなるということであり,亀裂の場合以上に,耐震上は,より不利な現象である。
② 美浜原発3号機配管破断死傷事故
2004年8月9日,福井県美浜町の関西電力美浜原子力発電所3号機(加圧水型軽水炉:PWR)において,配管が破裂し,高温高圧水蒸気の直撃を受けた作業員4人が即死,7人が全身火傷の重軽傷を負い,うち1人が2週間後に死亡するという痛ましい事故が発生した。破裂した炭素鋼配管は,直径56センチ,厚さ1センチもある大きなものであったが,破裂した箇所では厚さ1ミリ以下に薄くなっていた。
③ 減肉の原因
配管破損の原因は,いわゆるエロージョン・コロージョンにより配管が徐々に削られていった結果,90気圧もの内圧に耐えられなくなって破裂したものと推定されている。
「エロージョン・コロージョン」とは,機械的作用による浸食と化学的作用による腐食との相互作用によって起きる減肉現象である。美浜原発3号機の破裂箇所の手前にはオリフィスがあって流れが狭められていた。「オリフィス」というのは,流れを狭めて圧力の差を測り,流速を調べる装置である。流れを狭められた水はその下流で乱れ,渦や気泡ができて配管を削り取る。それが浸食(エロージョン)である。表面が腐食(コロージョン)されているとそれが起こりやすい。このエロージョンとコロージョンが繰り返し起こって配管の減肉が進んだと考えられている。
④ BWRの減肉管理
美浜原発3号機はPWR(加圧水型)であるが,被告浜岡原発を含むBWR(沸騰水型)も配管の減肉と無縁ではない。BWRでは,配管の破断が原子炉の冷却機能の喪失に直結することから,むしろ,より厳格な減肉管理が求められる。
美浜原発3号機の事故をきっかけに,エロージョン・コロージョンによる減肉が各原発で進行していて,いつ壊れてもおかしくないという事例が次々と明るみに出た。例えば,BWRでは,女川原発1号機,2号機において,炭素鋼より,エロージョン・コロージョンに強いと言われているステンレス鋼製配管へ取り替えたにもかかわらず,大きな減肉が続いていた。なお,コロージョンが少ないはずのステンレス鋼でなぜそうなるのか,原因はよく分かっていない。
こうして予測より速いスピードで減肉が進む場所があることが既に明らかとなっている。
⑤ 浜岡原発における減肉事例
被告野浜岡原発においても過去に,減肉貫通事例(3号機),激しい減肉事例(4号機)が確認されている。
⑥ 配管肉厚の管理指針
管理指針によると,配管の部位と使用条件などから初期の減肉率を決め,それから最低限必要な肉厚に減肉するまでの時間(余寿命)を予測し,余寿命が尽きる2年前までに配管肉厚を測定し,次の余寿命を決めることになっている。しかし,初期減肉率を決め間違うと,余寿命が極端に長くなってしまって,実際上検査が行われなくなる配管が出てきてしまう。
これは,定期的に検査しチェックしてゆく方法に比べ,危険な方法である。手間のかかる検査のコストを削減しようという発想から,このような指針になっているとしたら,早急に改めなければならない。原子力発電所における安全審査の趣旨は「災害が万が一にも起こらないようにするため」(伊方最高裁判決)にあり,その趣旨は,当然,管理指針にも及ぶはずだからである。
⑦ 小括
浜岡原発の減肉の全ての実態は未だ明らかになっていない。2012年2月15日,原子力安全委員会の斑目春樹委員長は,国会の福島第一原発事故調査委員会(黒川清委員長)が国会内で開いた第4回会合において,「国際安全基準に全く追いついていない。30年前の技術で安全審査をしている。早急に直さないといけない。ストレステストもあるし,指針類の改正もある。合わない炉は廃止し,世界最高の安全水準を目指す必要がある。」(2012年2月16日付中日新聞朝刊)と述べている。
被告は,この斑目委員長の発言を真摯に受け止め,減肉率が高い事例や必要最小肉厚に切迫した事例などについて,その実態を明らかにすべきである。そして,すべての減肉を破断に至る前に発見することができるというのであれば,それを証明すべきである。
(3)中性子照射脆化
① 老朽化原発の中性子照射脆化の概要
中性子照射脆化による原子炉圧力容器の破壊は,究極の大事故というべきもので,圧力容器が割れてしまった場合は,核反応の暴走を防ぐ手立てはほとんどない。絶対に起こしてはならない究極の破壊である。
中性子照射脆化の目安となるのが脆性遷移温度(割れやすくなる境の温度)である。もし,地震などによって配管が破断するという緊急事態が起きたら,緊急炉心冷却装置(ESSC)で炉心を急速に冷やさなければならないが,脆性遷移温度が高いと,その操作が危険になる。すなわち,急冷した時に圧力容器の内壁と外壁とで温度差が生じ,内壁には強い引張応力が作用するところ,脆性遷移温度以下でこのような力がかかれば,圧力容器全体が,バリンと破壊してしまう危険があるのである。この脆性遷移温度は,金属に中性子が当たると徐々に上昇することが知られている。
② 電力会社の照射脆化対策
圧力容器は,他の機器・配管と異なり,原子力発電所の心臓部でありその機能と巨大さから,取替は不可能である。したがって,圧力容器が老朽化して寿命に達したときは原子力発電所そのものを廃炉にするしかない。そのため,電力会社は,原子炉設置許可申請の段階で,圧力容器鋼材の原子力発電所供用期間中の中性子照射量を計算し,供用期間末期における脆性遷移温度を予測して,供用期間末期においても脆性遷移温度よりも余裕を持って高い温度で運転できることを確認すること,圧力容器内に圧力容器と同じ製造履歴を持つ鋼材から切り出した「監視試験片」を多数挿入配置して圧力容器鋼材の脆性遷移温度を把握することを要求され,実施している。
③ 脆化予測式とその改定
材料試験炉での加速試験(通常以上の荷重をかけたり,通常以上の高速で運転するなどして耐久性を調べるテスト。BWRであれば,40年間分を1~2日間で照射することになる。)によるデータを使って,照射脆化予測式というものが従来から作られてきた。
これは,脆性遷移温度の上昇を材料因子(鋼中の不純物原子の種類と数)と中性子照射量の関数として求めるものであった。
しかしながら,近年,廃炉となった原子炉の圧力容器鋼材そのもののデータや各種の研究によって,単位時間あたりの中性子照射量が少ない(照射速度が遅い)方が同一照射量に達したときの照射脆化が大きいことが明らかになった。具体的には,照射速度の遅いBWRにおいて,炉内の通常試験片と加速照射試験片の測定結果が合わないことがはっきりしてきたのである。ここから,脆性遷移温度の上昇には,中性子の照射量だけでなく,その照射速度も影響を及ぼしていることが判明した。
そこで,監視試験方法の照射脆化予測式は改訂され,新しい監視試験方法JEAC4201-2007が作られた(日本電気協会原子力規格委員会:原子炉構造材の監視試験方法JEAC4201-2007)。現在,圧力容器の評価は,新旧2つの監視試験方法の予測式を併用する移行期に当たっている。
④ 玄海1号炉圧力容器の想定外の脆化
2010年10月25日,九州電力は,唐津市議会プルサーマル特別委員会において,2009年4月の定期検査の際に取り出した玄海1号炉第4回監視試験片の脆性遷移温度が98℃に達していることを公表した。
前回(第3回)の監視試験結果(1993年2月)では脆性遷移温度は56℃であった。それが予測の範囲を超えて42℃も上昇した。今回のデータは,ばらつきによる誤差を加えて予測した上限を大きく超えるものであり,これは想定外の脆化が起こっていることを意味する。
前述したように,従来の脆化予測式は既に不正確であることが判明している。では,2007年に制定された新しい脆化予測式でこの玄海1号炉の高い脆性遷移温度が説明できるかというと,答えは否である。最新の2007年予測式によっても玄海1号炉の照射脆化挙動は再現できない。玄海1号炉に関しては,従来の予測式も2007年予測式も予測能力を失っているのである。
⑤ 浜岡原発における照射脆化の進行
被告は「本件原子力発電所では,材料の脆性遷移温度の初期値及びその上昇の程度が,材料の種類,材料中の不純物の含有量,材料に対する熱処理の方法によって左右されることを踏まえ,圧力容器の材料として,高い延性かつ靱性を有する低合金鋼を使用し,不純物の含有量を十分低く抑えるとともに,焼入れ・焼戻しの熱処理を施している。また,運転上の制限値として,脆性遷移温度に十分余裕を持たせた冷却材温度制限値を定め管理を実施するとともに,圧力容器の中性子照射による脆化傾向の監視を実施している。」と主張する(被告準備書面⑴56頁)。
しかしながら,本件原発はいずれもBWRであり,照射速度が遅いことから設置許可申請において予測していたよりも照射脆化が進行しているおそれが強い。実際,浜岡4,5号機の脆性遷移温度は予測を上回っていたことが最近報道されたところである(2012年2月12日付読売新聞朝刊)。また,上述のように脆化予測式を遥かに超えて脆化が進行していた玄海1号炉のケースに鑑みれば,本件原発の圧力容器の照射脆化が予測式以上に進んでいないか,被告は速やかにその詳細を明らかにすべきである。
⑥ 小括
原子力発電所の危険性は,地震・津波だけによるものではない。原発の老朽化も大きな危険要因である。圧力容器の照射脆化はその中で最も基本的な留意事項である。照射脆化などにより老朽化した圧力容器が想定される東海地震によく耐えうるのか,被告はその安全性を立証すべきである。
(1)いわゆる冷戦終結後,大量の核兵器による核戦争の危機が減少したといわれる一方,核兵器の拡散,放射性物質を用いたテロの脅威が叫ばれて久しい。しかし,2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震で発生し現在も収束の目途すらたっていない福島第一原子力発電所の事故は,核兵器など用いなくとも,原子力発電所を破壊し,大量の放射性物質を拡散させれば,一国を壊滅させるに十分であることを世界中に知らしめた。
(2)原子力発電所の諸施設を対象に考えられる「テロ」としては,核物質の奪取,原子炉施設の破壊(航空機,通常兵器を利用したものなど),電源を喪失させること,原子炉制御系システムへのサイバーテロなどが考えられよう。
(3)これに対し,電力会社側の対応は牧歌的といっても過言ではない。すなわち,対テロ対策として,「原子力発電所では,発電所内で保管されている核物質の盗取や,施設への妨害,破壊行為を想定して,従来より様々な防護措置を講じています。例えば,監視カメラや防護フェンスを設置したり,金属探知機等による持ち込み品の検査やIDカード等によるチェックを行ったりしています。さらに,万一の場合には治安当局と連携し,速やかに対処できるようにして」おり,航空機事故に対しては,「原子力発電所は構造上,航空機の落下を想定して設計されてはいません。現在の設計における考え方は,航空機が原子力施設に落下する確率を評価し,その確率が極めて小さいことから航空機の落下に対する設計上の考慮は必要ない,というものです。これは原子炉の設置に際しての安全審査において確認されており,国内の全ての原子力発電所において同様です」とのことである。(東京電力のHPから抜粋)
(4)1997年9月,当時の橋本龍太郎内閣のもとの安全保障会議において,原子力発電所のテロ対策が検討されたことがあるが,結果的に,「何重もの安全対策が講じられている」として原子力発電所の安全性を強調するに留まった。
2011年7月,自由民主党は,「原発警備に関する検討会」を設置し,同年9月15日,「福島第一原発の警備について…自衛隊が…対処すべき」「その他の原発…についても…警察の装備の充実,原発等警備隊の創設,自衛隊の任務に原発施設等の警護を加える」などの提言を行っている。
2012年2月22日,原子力・安全保安院は,想定を超える深刻な原発事故を防ぐための対策を検討する初めての会議を開催し,「テロや航空機事故といった,これまで考えてこなかった事故も具体的に検討すべきだ」との意見が出された。
2012年2月23日,日本政府は,同年3月26日から開催されるソウルでの核安全保障サミットにおいて,原子力発電所へのテロ攻撃により全電源喪失した場合に備えて電源確保のバックアップシステム構築を提案する方針である。
(5)しかし,わが国は海洋に囲まれた島国であり,わが国の原子力発電所は,全て沿岸部に設置されている。そして,原子炉施設は,構造的に海水による冷却を継続しなければならないところ,海水の取水系配管1つを破壊されただけで,深刻な事故を惹起するおそれは極めて高い。原子力発電所をテロの脅威から完全に護ることは不可能である。
以上
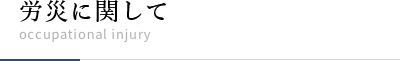
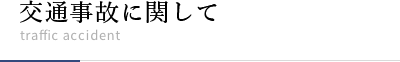
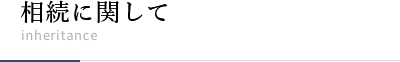
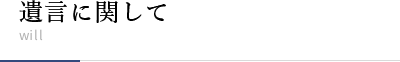
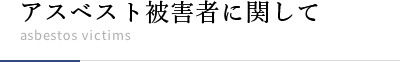
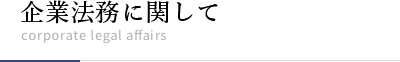
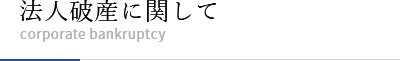
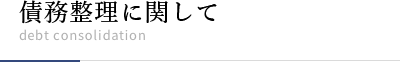
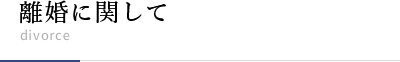
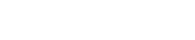
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348
平日法律相談 09:00 - 17:30 土曜法律相談 10:00 - 16:00