静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階


ここでは準備書面を掲載させていただきます。下記よりご覧いただければ幸いでございます。
>>浜岡原子力発電所運転永久停止請求事件の準備書面(ダウンロードはこちら)
平成23年(ワ)第425号,474号,745号、平成24年(ワ)第76号
原 告 清水澄夫・外
被 告 中部電力株式会社
準備書面(2)
2012年6月5日
静岡地方裁判所浜松支部民事部合議A係 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士 田代 博之
弁護士 小林 達美
弁護士 大橋 昭夫
弁護士 森下 文雄
弁護士 塩沢 忠和
弁護士 杉山繁二郎
弁護士 阿部 浩基
弁護士 久保田和之
弁護士 池田 剛志
弁護士 杉尾健太郎
弁護士 靍岡 寿治
弁護士 小池 賢
弁護士 鈴木 淳
弁護士 平野 晶規
弁護士 加茂 大樹
弁護士 末永 智子
弁護士 山形 祐生
弁護士 北村 栄
目 次
あの3.11から1年が経過した。史上最大最悪の公害といわれる福島第一原発の事故は,1年を経ても未だ大きな被害を及ぼし続けているが,人々の原発に対する意識は,この1年で大きく変わった。日々のテレビや新聞等のニュースで,人々の意識の変化とその行動は,裁判所には顕著だと思われるが,身近な新聞記事で(静岡・名古屋版を中心に)この点を明らかにしたい。なお,これらは報道された一部であり,文字通り草の根的に各地で多数の集会等が行われた。
たくさんの様々な市民たちが,原発のない日本を目指して,日本列島各地でそれぞれの地元で,草の根の「さよなら脱原発」の集会やパレード,講演会を企画し,行った(資料1~7)。地元静岡では,原発をなくそうをスローガンに「3.11メモリアル行動」として,静岡市や浜松市など8市2町で,集会・パレード・講演会が行われた。静岡市で開かれた「3.11メモリアルひまわり集会」では1100人もの人々が参加した(資料2の2)。名古屋でも「明日につなげる大集会」が行われ,約5000人が参加し,集会とパレードを行った(資料1,2の1,3の2,4,5)。被災地の地元福島では,「3.11福島県民大集会」が行われ,郡山に約1万6000人が駆けつけた(資料2の3,3の2,5,6)。東京では日比谷公園に約1万4000人,井の頭公園には約8000人が,永田町では国会議事堂を1万人以上が取り囲み「人間の鎖」を作った(資料2の1,5,7)。大阪では,大阪市内だけで「なくそう府民集会」など大規模な集会が2カ所であり,計約1万5000人が参加した(資料,2の2,5)。このように,全国各地で,脱原発に向けて人々の意識は大きく変わりつつある。
日本以外の世界でも,1周年を区切りに脱原発の動きが活発になっている(資料7~11)。韓国のソウルでも脱原発を訴える集会が開かれ,市民ら5000人以上が参加した(資料8)。ドイツでも「フクシマは警告する-原発いま閉鎖を」を合い言葉に,6つの原子力関連施設周辺でのデモに約2万人が集まり(資料9),ブラウンシュワイク周辺では2万4000人が参加し,たいまつに火をともしながら全長約80キロの「人間の鎖」をつくり原発反対を訴えた(資料10)。原発大国のフランスにおいても,市民グループが原発や各関連施設が密集する地域の約230㎞を断続的に手を繋いで結ぶ「人間の鎖」を実施し,約6万人が参加し,同国では過去最大規模の反原発の催しとなった(資料7,9)。スイスでも約8000人が原発の運転の即時停止を求めるデモを行った。さらに,台湾でも約3000人が原発ゼロを掲げてデモ行進が行い(資料11),イギリスではデモと座り込みが(資料7,11),アメリカでも脱原発を訴える集会が行われた(資料10,11)。このように,世界レベルにおいても,福島第一原発事故は大きな影響を及ぼし,脱原発が世界の大きなうねりとなってきている。
現時点(2012(平成24)年5月17日)において,我が国で稼働している原発は0であるが,3.11から1周年の節目の時期を迎え,中日新聞が静岡大学と共同で浜岡原発の再稼働についての静岡県民の意識調査を行った(資料12~14)。その結果,再稼働に反対する人は68%,菅前首相の停止判断を支持する人は86%にものぼった(資料12)。また,再稼働について静岡県内の全35市町の首長に質問した結果,6割の21市町の首長が否定的であった。原発から半径30㎞圏の11市町で見ると,再稼働賛成は地元の御前崎市長だけで,8市町長が反対している(資料12~14)。また,静岡新聞の全国世論調査では,原発への依存度を段階的に下げ将来は原発をなくす「脱原発」という考え方に「賛成」(44%),「どちらかといえば賛成」(36%)を合わせると80%に上ることが,震災後1年の全国面接世論調査で分かった(資料15)。また,静岡新聞の浜岡原発の再稼働についての県民アンケート調査では,回答者の5割以上が「再稼働は認めず廃炉にすべき」と考えていることが分かった(資料16)。さらに,県内の全35市町を対象とした自治体のアンケート調査では,浜岡原発の地元4市(御前崎,牧之原,菊川,掛川)を含む17市町が「東京電力福島第一原発事故が未だに収束しない中,住民の理解が得られない」などを理由に明確な回答を避けたりして無回答の市町も多かったが,「再稼働は認めず廃炉にすべき」と回答した自治体は34.2%あり,その前年の6月の調査時と比べて22.8ポイントも上昇した(資料16)。さらに,浜岡原発の再稼働について,静岡市葵区での街頭投票では,2時間ほどで865人が回答し,「永久停止・廃炉には賛成」が704人(82%),「再稼働に賛成」が78人(9%),「わからない」が83人(9%)であった(資料17)。このように,浜岡原発の再稼働については,多くの県民及び市町が,反対の意思表示をしているだけでなく,廃炉までも望んでいる。
3.11から1年,私たちは変わったのだろうか,これが今問いかけられている。国も県も変わっていないのではないか(資料18)。現状はどうか。政府は原発の再稼働に前のめりになり,原発の海外輸出に何のためらいもなく,国民の知りたいエネルギー計画は進んでいるようには見えない。日本の原子力政策は何も変わってないように見える。従って,政治が変わらなければ政治に頼むのではなく,私たち自身が変わらねばならない。主権者である私たちが変わらねばならないのである。そして,私たちが前進するためには絶えざる自戒と反問が必要である。1年前の不幸な出来事は,恐るべき程多くの犠牲のうえに,未来の真剣な考察を私たちに重く課した。私たち一人ひとりが変わらねばならないのである(資料18)。残念ながら,裁判所も,これまで原発訴訟が提起されてから30年以上,「国策」を前に,原発に正面から向き合ってこなかったことが指摘されている(資料19)。確かに,原発を進めるか否かは民主主義のルールで国民自身が判断することだが,司法は司法の立場で,正しく誠実に原発及び原発事故の危険性と向き合って,人権の最後の砦としての役割を果たすべき時が,今こそ来ている。国や県などの行政に対する不信が未だ根強く続いている中,史上最大最悪の公害に見舞われ歴史的転換期の真っただ中の今,司法への信頼までもが決して失われてはならないと考える。
被告は,準備書面(1)34頁以下で「地震に係る安全性」,50頁以下で「津波に係る安全性」,65頁以下において「改訂指針に照らした耐震安全性の評価・確認」について述べているが,今となっては,これら被告の主張は,浜岡原発の耐震安全性や津波に対する安全性を何ら論証するものではなく,ほとんど無意味な主張である。なぜなら,第1に,福島第一原発事故を踏まえて,耐震設計審査指針そのものの改訂が必至だからである。第2に,内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会(*)」は,あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波を検討していくべきだとの方針に基づいて検討し,その結果を2012年(平成24年)3月31日に「南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高について」として発表したが,それによると,地震の規模は最大でMw(モーメントマグニチュード)9.0~9.1,浜岡原発のある御前崎市では,震度は最大で7,津波高は最大で21.0mという推計となっているからである。今後は,この推計が防災対策の基本となるべきである。同モデル検討会は「今回の推計結果は,決して,南海トラフ沿いにおいて次に起こる地震・津波を予測したのではない」「別の言い方をすれば,現在の科学的知見の下で,今回推計し設定する最大クラスの地震・津波の発生率,そしてその時期を予測することは不可能だ」と断っているが,福島第一原発のような過酷事故は今後起こることは絶対に許されない事故であるから,浜岡原発の耐震安全性,津波に対する安全性を評価するに当たっては,現時点で予測される最大クラスの地震,津波を基準とするのは当然のことである。したがって,被告の耐震安全性,津波に対する安全性の主張は,この推計に基づいて全面的に改められなければならない。
*南海トラフの巨大地震モデル検討会について
中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」中間報告を踏まえ,南海トラフの巨大地震である東海・東南海・南海地震について,新たに想定地震を設定していくためには,これまでの科学的知見の整理・分析が不可欠であるとの認識のもとに設置された検討会で,過去に南海トラフのプレート境界で発生した地震に係る科学的知見に基づく各種調査について防災の観点から 幅広く整理・分析し,想定すべき最大クラスの対象地震の設定方針を検討することを目的とする。理学・工学等の研究者から構成されている。
運転中の原子炉内部では核分裂連鎖反応が起きている。また,使用済み核燃料であっても,放射性核分裂生成物等が崩壊熱を出し続ける。これら炉心燃料や使用済み核燃料の冷却に失敗したり,核分裂反応の制御に失敗すれば,核燃料の溶融が起こり,また水素爆発などによって,大量の放射性物質が放射性微粒子となって全地球規模にわたる環境中にまき散らされることは,現在進行中の福島第一原発事故が物語っている。
原子炉内部における核分裂連鎖反応の結果,プルトニウムなど微量でも激甚な被害を環境に与える放射性核分裂生成物が多数生成される。そして,原子炉内部で生成される放射性物質は核種ごとの半減期に応じて減少していくことを待つしかないところ,その中には非常に半減期の長い核種が多く含まれており,一旦環境中に放出されれば,半永久的と言ってもよい長期間にわたって環境中に留まり影響を与え続ける。すなわち,原子力発電所の過酷事故によって放射性物質が環境中に放出されれば,その被害は不可逆的で,広範囲かつ半永久的に環境に対して取り返しのつかないダメージを与え続け,人間を含む生物の生存できる環境が失われる可能性がある。
(1) 放射線の被曝態様
原子力発電所の過酷事故によって引き起こされる放射線による人体への影響は,様々な経路をたどってもたらされる。もちろん,1999年(平成11年)9月30日に起きた東海村JCO臨界事故のように核分裂反応の制御に失敗すれば,原子炉の至近距離にいる人間が直接中性子線等の放射線を浴びることも考えられるが,以下では,放射性物質が環境中に放出された場合を考える。核分裂生成物等の放射性物質が環境中に放出された場合,放射線による人体への被曝態様は,人体の外部から放射性物質の出す放射線に被曝する外部被爆と,放射性物質を呼吸や飲食等により体内に摂取することによって放射性物質の出す放射線に被曝する内部被曝とがある。
(2) 放射性物質による外部被曝
原子炉内部における核分裂連鎖反応の結果,大量の放射性核分裂生成物が生成される。これらの放射性核分裂生成物は,主にベータ線やガンマ線を放出する。また,核燃料中の未分裂のウラン235も,自らアルファ線を放出し,次々と種類の違う放射性原子に姿を変えながら,ガンマ線やベータ線を放出する。これら放射性物質が放射性微粒子となって環境中に放出されると,人間のの皮膚や髪,衣服に付着し,あるいは大気中および地面から,アルファ線,ベータ線及びガンマ線を放出して身体の外から放射線被曝を引き起こす。
(3) 放射性物質による内部被曝
ア 放射性微粒子は,あるいは呼吸により体内に取り込まれて肺胞に達し,あるいは飲食物を通じて腸管に達し,血管やリンパ管を通じて身体の中を移動し,組織や器官に沈着して,これらの組織の細胞に身体の中から放射線を浴びせ続けることになる。かかる内部被曝は,次の4点において外部被曝とは異なった態様で人体に深刻な影響を及ぼす。
①放射性物質による放射線が放出するエネルギーは線源から離れるほど減衰するところ,体内では近傍の細胞に極めて大きなエネルギーを吸収させる。
②アルファ線,ベータ線は短い飛程の中で集中的にエネルギー放出するところ,沈着した周囲の細胞の染色体(遺伝子)を切断する。
③自然放射性核種と異なり,ウラン235が分裂して生成される人工放射性核種は,核種の種類に応じて特定の組織や器官に沈着し,当該組織や器官が集中的に被曝する。
④体内に取り込まれた放射性核種は,その核種の半減期に応じて継続的に被曝させ続ける。
イ 内部被曝の影響の複雑さ
体内に取り込まれた放射性物質が人体に影響を与える機序については,上記のとおり極めて複雑である。しかも,放射性物質を体内に取り込んで,低線量の放射線を長い期間をかけて浴びせ続けることになるので,放射線障害が遅れて発症することも考えられる。
(4) 放射線による人体影響の現れ方(放射線障害)
ア 放射線急性障害
放射線被曝による急性障害の症状は,脱毛,悪心,吐き気,嘔吐,食欲不振,口内炎,下痢,下血,血尿,鼻出血,歯齦出血,皮下出血,生殖器出血などの出血傾向,脱力感,全身倦怠感,発熱,口渇,喀血,咽頭痛,白血球減少,赤血球減少,無精子症,月経異常などの諸症状である。その機序は次のとおりである。すなわち,放射線,とりわけ人体への破壊力が大きな中性子線を浴びた人体内では,腸などの消化器系の内臓,血液を造る骨髄などで,細胞が自らの機能を停止させ死んでいく細胞自殺(アポトーシス)を起こす。そのため,内臓機能が低下したり,造血不良が起こって死に至ることもある。死に至らない場合でも,消化器系の粘膜は放射線に対する感受性が高いため,たとえば,胃腸の粘膜の場合には剥離をしたり,びらんを起こしたりして,自覚症状として,悪心,嘔吐,下痢などの急性障害として現れる。
イ 放射線晩発性障害
放射線被曝による晩発性障害としては,白血病を含むガン,白内障,心筋梗塞を始めとする心疾患,脳卒中,肺疾患,肝機能障害,消化器疾患,晩発性の白血球減少症や重症貧血などの造血機能障害,甲状腺機能低下症,慢性甲状腺炎などが知られている。その機序は次のとおりである。
すなわち,放射線は,原子の中心にある原子核の周りを回る電子にエネルギーを与え,電子を原子から外にはじき出してしまう(電離作用)。電子は分子を結合する役割を果たしているが,その電子がはじき飛ばされると,結合していた分子は壊れてしまう。具体的には,体内のDNAのらせんの間を鎖のように結ぶアミノ酸が放射線を浴びて切断され。これが一箇所だけ切断された場合には,ほとんどが元の正常な形に修復されるが,集中的に破壊作用が起きると修復機能が正常に機能せず,様々な障害を引き起こす原因になる(放射線の直接作用)。かかる放射線の直接作用は,一般にも広く認識されているが,放射線が障害を及ぼす機序は直接作用だけによるのではない。ガンマ線が細胞の中の水分子に当たると,水がプラスイオンとマイナスイオンに電離し,そのマイナスイオンがDNAの二重らせんに到着すると,化学反応を起こして二重らせんを切断する(放射線の間接作用)。これが一箇所だけ切断された場合には,ほとんどが元の正常な形に修復する機能を保つが,これが集中的に生じると,修復を誤るなどの事態が生じて,深刻な症状を引き起こすことになる。ガンマ線が体内の原子の中に衝突すると,電子がそのガンマ線のエネルギーをもらって走り出す。その電子は電気を帯びているので,次々と周辺の原子の中の電子にエネルギーを与え,どんどんそれらの電子を跳ね飛ばす(密度の低い電離作用)。一方,中性子は,電荷を持っていないので直接電離作用はしないが,中性子が人体の中の陽子にぶつかると,電気を持った陽子が走り出し,この陽子が集中した電離作用を引き起こす(密度の高い電離作用)。いずれも身体に深刻な影響を与える。このように,放射線はDNAを損傷し,遺伝的な影響,晩発性のガンを引き起こすなどの重大な影響を与えるが,それだけでなく,細胞膜などの破壊による深刻な被害を引き起こす。つまり,放射性物質が細胞に取り込まれた結果,そこでベータ線等を出せば,細胞の膜が傷つけられることが当然起こる。ベータ線の場合は,ガンマ線に比べて一定の距離を進む間に起こす電離の数が多いので,ガンマ線の場合には素通りしていったり,まばらにしか電離作用を起こさないのに比べて,ベータ線ではもっと濃密度で起こすので,細胞膜が傷つくことが起こり得るのである。もちろん,これらが内部被曝単独で生じるのではなく,外部被曝の影響も合わせて起こりうるものであり,放射線の人体影響を考える場合には,両方の影響を考慮する必要がある。また,酸素は細胞の中に取り込まれ,命を作る運動(代謝)をする。放射線がこの酸素にぶつかると電気を帯び,人体に有害な活性酸素に変化する。電気を帯びた活性酸素は,人間の細胞を防護している細胞膜に影響して穴を開ける。その中に放射線が入った場合の影響については,科学的には解明されていないが,放射線による桁違いのエネルギーにより新陳代謝が大きな影響を受けて動揺し不安定になると考えられる。影響を受ける細胞が体細胞,つまり胃や肺,肝臓という臓器である場合には,突然変異を受けてがん細胞に変わっていき,生殖細胞の場合には,遺伝子に傷がついて遺伝に障害が生じる。さらに,初期の物理的過程により,原子や分子の化学的結合が切れて放射線分解が起こると,遊離基(1個又は複数個の不対電子を有する原子や分子で,フリーラジカルという。)が生成する。これを物理的化学的過程といい10億分の1秒程度の時間内に起こる。人体内に放射線が入ったときに生成する遊離基は,人体の主成分である水分子の変化したものが多い。遊離基は極めて不安定で非常に反応性に富むため,他の遊離基又は安定分子と直ちに反応する。遊離基が生物学的に重要な分子である細胞内のタンパク質や核酸と反応して変化を起こし,結果として細胞に損傷を与える(放射線の間接作用)。これらの放射線の直接作用,間接作用による放射線の人体への影響は,遺伝子に影響を与えて悪性腫瘍を発症させるだけではなく,中間因子としての炎症や免疫異常,更にはホルモンへの影響等を通じて様々ながんそして,非がん疾患を発症させることが,財団法人放射線影響研究所による疫学的研究や免疫学的研究に徐々に明らかになりつつある。
(1)使用済み核燃料の危険性
原子力発電は燃料のウランを連続的に核分裂させ,そのとき発生する熱で蒸気をつくり,タービンを回して発電する。つまり,原子力発電における燃料はウランである。ウランを燃料として使用すると,使用済みの核燃料と呼ばれる物質が核燃料棒に残る。使用済み燃料中に含まれる物質は,核分裂生成物(「死の灰」と呼ばれる),燃え残りのウラン,新たに生成されたプルトニウム等であり,それらの物質が渾然一体となって生成される。核分裂生成物(死の灰)は,高レベル放射性廃棄物である。高レベル放射性廃棄物は,プルトニウム238,プルトニウム239,セシウム134,セシウム137,クリプトン85等といった多種多様な放射性物質の塊である。こうした放射性廃棄物は以下の特徴を有している。
ア 放射能が強い
高レベル放射性廃棄物は非常に強力な放射線の発し続け,人が近づけば数十秒で死に至るほど致死性の高い物質である。
イ 発熱が大きい
放射能による発熱は大きく,高い発熱によってメルトダウンの可能性もある。また,埋蔵すれば地下に熱の塊をつくり,周りの地層に影響を与える可能性がある。
ウ 毒性が強い
高レベル放射性廃棄物には,ストロンチウム90,アメリシウム241といった放射能毒性が強い元素が含まれている。
エ 半減期が長い
高レベル放射性廃棄物の中には,プルトニウムやアメリシウム,ネプツニウムといった半減期が非常に長い物質が含まれている。例えば,プルトニウム238の半減期は88年,プルトニウム239は2万4100年,アメリシウム241は432年,ネプツニウム237は214万年である。半減期が長いということは,放射能の毒性も長期間継続するということである。容器や施設での長期間の保管が必要となるが,長期間に渡る容器等の健全性は保証されていない。
(2)浜岡原子力発電所における保管の危険性
ア 浜岡原発における保管状況
浜岡原子力発電所(以下「浜岡原発」という。)においても,同発電所で生じた使用済み核燃料が保管されている。被告ホームページによれば,平成23年10月末の時点で,6625本の使用済み核燃料が浜岡原発内の使用済み核燃料プールで貯蔵されている。平成21年9月末の時点において,浜岡原発の使用済み核燃料管理容量は,1740tU(注:tUとは,ウラン換算重量(トン)。),同原発の貯蔵量は1080tUであり,貯蔵量は,約62%に達している(平成21年版原子力白書)。
イ 今後の予想
浜岡原発の1炉心の燃料は410(tU)であり,1取替分は100(tU)である(平成21年版原子力白書)。燃料は,3年から5年ごとに取り替えられる。
浜岡原発において,仮に,4号機と5号機が稼働した場合,3年から5年の間に,200tUの使用済み核燃料が生じる。今後,今と同様に再処理が行われず,燃料を運び出せない状況下で原発を稼働させた場合,早ければ10年後には燃料貯蔵プールが満杯になり,貯蔵する場所がなくなってしまう。現に,平成21年度以降,浜岡原発から使用済み核燃料が搬出された実績はない(被告ホームページ内,浜岡原子力発電所実績データ)。
ウ 浜岡原発における保管の危険性
(ア)冷却の必要性
原子炉内で燃料であるウラン235が核分裂すると,様々な種類の原子核に分裂し,100種ほどの核分裂生成物ができる。そのほとんどが不安定な放射性物質であり,これらは安定した状態になるまで放射線を出しながら高い熱を出し続ける。核分裂生成物の種類によっては,これが数万年以上続く。この熱によって廃棄物が溶けてしまうおそれがあるため,すぐに処分することができない。また,地下に埋設する場合でも,地下に「熱の固まり」を埋めることになり,周りの地層に影響を及ぼす可能性がある。したがって,発熱量がある程度下がるまで,何年かは水に入れて継続的に冷やす必要がある。
(イ)地震時に想定される危険
a 水面上への露出
燃料プールに保管されている燃料には,使用が終了して長期間経っているものもあれば,前回の定期点検で取り出されたばかりのものもある。後者は,まだ高い熱を発しているため,これが水面上に露出すると燃料の溶融が生じる。したがって,地震によって燃料プールが破損して水が流出し燃料が露出した場合には,燃料の溶融が生じる。福島第一原発の4号機の使用済み核燃料プールはこのような危機に直面していた。 また,燃料プールの冷却ポンプが故障した場合には,燃料プールの水が燃料が発する熱によって沸騰して水が蒸発し,水位が下がる危険性がある。
現に,福島第1原子力発電所の事故においては,電源喪失によって使用済み核燃料プールの冷却が停止したため,使用済み核燃料の発熱による水の蒸発により,水位が低下し続けた(原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書-東京電力福島原子力発電所の事故について-8頁)。
b 燃料ラックの崩壊
地震の揺れ等によって燃料の入ったラック(格子)が崩壊し,燃料が崩れたり倒れたりすると,燃料の溶融が生じる危険性が高い。すなわち,燃料が倒れたり崩れたりすることによって,倒れた燃料の間に水が入らなくなると,その部分に熱が溜まり,その部分の水が蒸発して空洞ができ,そこにある燃料が溶ける可能性がある。また,燃料同士が,炉心の中に入っていたときと同様の位置関係と距離になれば,再臨界(注:臨界とは,中性子の生成と消失の均衡が保たれ,核分裂連鎖反応が同じ割合で持続している状態をいう。原子力発電所では原子炉を臨界状態に保つことにより発電を行う。再臨界とは,臨界から未臨界状態に移行後,再び臨界になることをいう。原子力安全保安院ホームページ原子力防災用語集より)が生じる可能性がある。地震の揺れによって建屋が崩壊し,燃料プールが崩れ落ちるなどして使用済み核燃料が再臨界を起こした場合,巨大な水蒸気爆発が発生する可能性がある。
(1)核燃料サイクルとは
原子力発電所の使用済み燃料を再処理してウラン,プルトニウム,高レベル放射性廃棄物に分離し,このうちウランとプルトニウムを取り出して混合し,混合燃料(MOX燃料)を作る。そうしたMOX燃料を「高速増殖炉」という特殊な原子炉を利用しながらプルトニウムを増やす。この流れが,いわゆる「核燃料サイクル」であり,日本ではこうした核燃料サイクル政策が採られている。使用済み核燃料から,プルトニウムとウランを取りだすための施設が再処理工場である。
(2)諸外国の方針
原子力発電所を運転している諸外国のうち,アメリカ,イギリス,フィンランド,ドイツなどは,プルトニウムを利用せず,使用済み核燃料をそのまま核廃棄物として処分する方式(直接処分,ワンススルー)を採っている。核燃料サイクル方式を採る国には,日本の他にフランス,ロシアがあるが,両国ともプルトニウムの増殖はすでに放棄している。なぜなら,高速増殖炉は,冷却剤に水ではなく,水と激しく反応するナトリウムを使用すること,軽水炉よりエネルギーの高い中性子を使用することなどから通常の原子炉と比べてさらに危険が大きいからである。
(3)再処理計画の頓挫
ア 再処理の概要
使用済み核燃料には,発電中にウランの核分裂によってできた核分裂生成物,燃え残りのウラン,新たに生成されたプルトニウムが含まれている。再処理とは,このプルトニウムと燃え残ったウランを,多種類の化学薬品を使って化学的に分離・処理し,もう一度燃料として使えるようにする処理である。プルトニウムとウランを取り出した後には,高レベル放射性廃液が残る。日本では,高レベル放射性廃液は,高温でガラスと混ぜ,ステンレスキャニスターという容器に入れて冷やし固め,ガラス固化体を製造し,処理するという方法で処分される。
イ 試験運転の段階でトラブルが連続していること
使用済み核燃料の再処理は,日本動燃株式会社が所有・運営する,青森県上北郡六カ所村内の六カ所再処理工場で行われている。六カ所再処理工場は,1993年に建設が開始され,1998年には使用済燃料プールが完成し,燃料の輸送が始まった。工場施設は,2001年に完成し,2004年から,操業前の試験運転(使用前検査)を行っている。しかし,試験運転ではトラブルが続出し,特に,2007年に開始された「高レベル放射性廃液を使ったガラス固化体製造試験」において事故が連続したため,操業の延期を繰り返している。
ウ 操業の見込みが立たないこと
現在,六カ所再処理工場は,2012年10月の操業が予定されているものの,日本原燃株式会社によれば,高レベル廃液ガラス固化建屋におけるアクティブ試験(通水作動試験や化学試験,ウラン試験という段階的な試験の一環として,操業前の最終段階として実施するもの。実際の使用済み燃料を用いて,プルトニウムや核分裂生成物の取り扱いに係る再処理施設の安全機能及び機器・設備の性能を確認する。具体的には,核分裂生成物の分離性能,ウランとプルトニウムの分配性能,環境への放出放射能量,放射性廃棄物及び固体廃棄物の処理能力などの確認を行う。)の進捗率は53%である(2012年3月31日現在,日本原燃株式会社ホームページ)。再処理工場の試験運転は,大量の電気を必要とする。東日本大震災,福島原発の事故による電力不足により,試験運転は計画通りには行われておらず,さらなる操業の延期が予想される。
(4)ガラス固化体の処理問題
ア ガラス固化体の危険性
仮に,再処理工場の試験運転が成功し,ガラス固化体を製造できたとしても,製造したガラス固化体の処分が大きな問題となる。ガラス固化体は,使用済み核燃料そのものと同様,高レベル放射性廃棄物である。すなわち,ガラス固化体は,高レベル放射性廃液とガラスを混ぜて固めたものであり,東海再処理工場で製造されたものを例にとると,高レベル放射性廃液が約15%,ガラス成分が約85%含まれている。ガラス固化体1本には,セシウム137に換算すると,広島原爆の約100倍の放射性物質が含まれており,約2キロワットの発熱があり,すぐそばに1分間立っているだけで,約200シーベルトもの放射線を浴びる。そばに人間がいれば,数秒で確実に死亡するほどの放射線量である。
イ 地層処分の危険性
日本では,ガラス固化体の処分について,地層処分(高レベル放射性廃棄物の最終処分としてガラス固化体を地下数百メートルより深い地層中に隔離する方法。経済産業省資源エネルギー庁放射性廃棄物等対策室ホームページより)によるとしている。ガラス固化体を30年から50年間貯蔵して,放射能の量が少し減り,発熱が約半分になるのを待って,地下数百メートルから1000メートルの深さのところに埋めるという方法である。高レベル放射性廃棄物は,少なくとも10万年以上は人間の生活環境から隔離しなければならない。しかし,もともと地層処分を発想して技術開発を主導してきたのは,地震活動が非常に低い欧米の安定した地盤を持つ大陸の国々である。日本においては,1962年に日本の原子力委員会の専門部会がまとめた中間報告において,「ちょう密な人口,狭隘な国土,複雑な地質構造,地震などの多い環境条件などから我が国においてはその実施が困難と考えられる」とされていた。そして,国土が狭い地震国では,最も可能性のある最終処分方式は深海投棄であるとしていた。ところが,1972年のロンドン条約で,海洋投棄が禁止されたために,日本でも「地層処分ができることにした」のである。火山,地震が多い日本では,地層処分の適地となりうるような安定した強固な地層はなく,人口が多いため,事故が発生した際の影響も大きくなる。原子力発電環境整備機構(NUMO)は,日本列島にも将来10万年にわたって十分安定で処分場に適した場所が広く存在するとしている。しかし,地盤の安定した大陸諸国と比べて,日本列島の地震活動の激しさや岩盤の破砕度は群を抜いている。また,ガラス固化体から漏れた放射性物質は地下水に溶出して運搬され人間環境に到達する危険があるが,地下水の動きは複雑で未知の部分が多い。NUMOは,地震に関して,「活断層がなければ大地震は起こらない」との認識を有しているが,誤りである。地震の本源は地下の断層運動であるから,今後10万年間には,地表付近の活断層とは関係なく,大地震が発生する可能性がある。10万年後には,日本列島のなかに地震の影響を受けなかった場所が皆無でないとしても,事前に安全な処分場を選定することは不可能である。
ウ 処分場候補地が見つからないこと
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律によれば,最終処分場の建設予定地を選定するためには,文献調査,概要調査,精密調査,最終処分施設建設地の選定の順で,段階的に候補地を絞り込んでいく必要がある。しかし,2011年9月の時点で,最初の段階である文献調査にも着手できていない。
(5)再処理で取り出したプルトニウムの利用
ア 高速増殖炉もんじゅ
高速増殖炉とは,原子炉冷却材にナトリウムを用いて中性子の減速効果を抑え高速中性子により燃料の増殖を図る原子炉である。日本には,独立行政法人日本原子力研究開発機構が運営する実験炉「常陽」(茨城県)と原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)がある。現在,両者ともに事故で運転を停止している。
イ プルサーマル発電
プルサーマルとは,ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料(MOX燃料)を従来のウラン燃料と同様に軽水炉で利用することをいう。ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料 [MOX燃料:Mixed(Uranium and Plutonium)Oxide Fuel]とは,二酸化ウラン(UO2) と二酸化プルトニウム(PuO2)を混合・焼結して作った核燃料である。もともと,高速増殖炉での利用が予定されていたが,現在,高速増殖炉が運転を停止しているため,作っても使い道がない。わが国は,高速増殖炉がすぐに実現できるという前提で使用済み核燃料の再処理をイギリス,フランスに委託したため,既に45トンものプルトニウムをため込んでしまった。六カ所再処理工場が稼働しなくても,既に大量のプルトニウムを保有している。プルトニウムは核兵器の材料になる。45トンという量は長崎型原発の4000発分に相当する。使い道のないプルトニウムを大量に保有することは国際的にも許されない。そこで,軽水炉でMOX燃料を燃やすことにしたのである。これがプルサーマル計画である。しかし,軽水炉はウランを燃やすために設計されているため,プルトニウムを含んだMOX燃料を使用すると,制御棒の働きの悪化や燃料棒の破壊等の危険性が生じる。
ウ 「もんじゅ」の破綻
核燃料サイクルは,使用済み核燃料の再処理によって取り出したプルトニウムを高速増殖炉によって増やし,発電に利用することを目的としている。ところが,核燃料サイクル構想の中心である「もんじゅ」が事故により運転を停止し,運転再開の見通しも立っていない。「もんじゅ」の運転再開の展望がない以上,核燃料サイクル構想を維持することは,もはや不可能である。
(6)保管場所の不足
ア 現在の保管状況
当初,使用済み核燃料は,再処理のため,六カ所再処理工場に運び込まれていた。しかし,再処理が進まないため,再処理工場に運ばずに各原発において貯蔵されるようになった。再処理が予定通りできない状況で原発を稼働させると,各原発で保管する使用済み核燃料の貯蔵量が増え,いずれ満杯になる。
イ 保管ラック(格子)の増設,リラッキング
各原発での保管容量を増やすため,燃料の保管ラック(格子)の増設やリラッキングが行われている。リラッキングとは,燃料プールの大きさは変えずに,燃料を収納する格子(ラック)の間隔を詰めて収納本数を増やす方法である。
浜岡原発においても,過去にリラッキングを行っている。しかし,リラッキングを行っても,いずれは満杯になってしまうため,急場しのぎの延命策にすぎない。また,燃料同士の間隔が狭くなることによって,それだけ冷却効率が下がり,核分裂の連鎖反応が始まる危険性がある。
ウ むつ市の中間貯蔵施設
中間貯蔵とは,原子力発電所と最終処分場という二つの施設の間で,放射性廃棄物を一定期間貯蔵することをいう。多くの場合は,原子力発電所で発生した使用済み核燃料や再処理で製造したガラス固化体(高レベル放射性廃棄物)を,最終処分場へ輸送するまでの間貯蔵することを指す。政府は,むつ市に,最終的な貯蔵量5000tUの中間貯蔵施設を建設中である。施設の事業開始は,平成25年10月と予定されている。ここに,全国の原発から使用済み核燃料が輸送されてくる。5000tUとは,一つの原子力発電所が1年間で生み出す使用済み核燃料の160~170倍であるから,その貯蔵量は膨大なものとなる。
(7)核燃料サイクルの破綻
政府は,「エネルギー資源の大部分を輸入に依存している我が国では,原子力発電所で発生する使用済燃料を再処理し,回収されるプルトニウム,ウラン等を再び燃料として有効利用する」ため,核燃料サイクル政策を基本方針としている(平成21年版原子力白書)。現在,茨城県にある実験炉「常陽」と福井県にある原型炉「もんじゅ」の2基の高速増殖炉は,いずれも事故を起こし運転を停止している。再処理によって取り出したプルトニウムを使用するはずの高速増殖炉が運転を停止し稼働していない以上,もはや再処理を行う必要性はない。六カ所再処理工場も運転再開の見通しが立っていない。しかし,前述のように,わが国はイギリスやフランスに再処理を委託して既に大量のプルトニウムを保有している。使い道のないプルトニウムを大量に保有することは国際的には認められない。苦肉の策として,プルトニウムを使うプルサーマル発電を開始したが,プルサーマル発電は危険性が高い上に,コストも大幅に増加している。したがって,核燃料サイクル政策はすでに破綻しており,見直しは不可避の状況にある。
(8)政府の方針転換
ア 処分方針の見直し
再処理が進んでいない状況を受けて,平成24年5月16日,内閣府原子力政策担当室原子力発電・核燃料サイクル技術等検討小委員会は,「代表シナリオの評価を踏まえた政策選択肢の総合評価」を発表し,処分方針の見直しを始めた。同委員会は,将来の原発への依存度に応じて,使用済み核燃料の再処理,地中廃棄,両者の併存の3方法を検討した結果,依存度が不透明な場合は政策の柔軟性があるとして併存が最も優れているとする総合評価をまとめた。併存策を選択した場合の措置について,同総合評価では,「六カ所再処理工場,J-MOX工場は稼働するが,六カ所再処理工場の能力を超える使用済み燃料は当面貯蔵する。貯蔵された使用済み燃料について再処理に取り組むとともに,直接処分の実施に向けた取り組みを始める」とする。
イ 地中廃棄の候補地の選定
地中廃棄を視野に入れているが,前述のとおり,現実的に受け入れ先を探すのは困難を極めることが予想される。受け入れ先が見つからないまま,地層処分を行うことを決めても,処分できないまま保管量が増える一方となる。同総合評価でも触れられているが,使用済み核燃料の貯蔵能力の増強が進まない場合,六カ所再処理工場が稼働していないため,各発電所の使用済み核燃料の管理容量の逼迫時期が前倒しになるのは明らかである。
ウ このように,直接処分方式を採用し,地中廃棄を選択した場合にも,再処理を選択した場合と同様に,放射性物質流出の危険性の問題,最終処分地の立地の問題に直面することになる。
以上のとおり,構想の中心である高速増殖炉が運転を停止し,再開の見通しが立っていない以上,すでに核燃料サイクルは破綻している。六カ所再処理工場もガラス固化体の製造工程のトラブルで運転を停止しており,再開の見通しは立っていない。したがって、現在の状況下で原発を稼働し続けると,浜岡原発をはじめ,各原発に使用済み核燃料が貯まる一方となる。これまでの再処理(イギリス,フランスに委託した分も含む)によって保有する大量のプルトニウムの処分方法,ガラス固化体の処分方法も決まっていない。仮に,再処理を止めて直接処分方式を導入し,処分方法として地中廃棄を選択した場合でも,放射性物質を完全に閉じこめられる保障はなく,また地中廃棄の受け入れ先の選定が難航するのは明らかである。現在の技術では,安全,確実なガラス固化体及び使用済み核燃料の処理方法などない。他方,福島第一原子力発電所の事故をはじめ,過去の例に鑑みれば,一旦事故が発生すれば,甚大で不可逆的な被害が発生することが明らかである。したがって,我々が採りうる選択肢は,これ以上使用済み核燃料を増やさないこと,すなわち,浜岡原発をはじめとする原子力発電所を廃炉にする以外にはないのである。
被告は,準備書面(1)51頁以下で「深層防護の考え方に基づく事故防止対策」について述べているが,福島第一原発事故では,このような何重もの安全対策がいとも簡単に破られてしまった。そのことの持つ意味は極めて重い。ところで,福島原発事故独立検証委員会(いわゆる民間事故調)の調査・検証報告書(2012年3月)では,事業者の安全対策のうち,過酷事故(シビアアクシデント)に対する対策・アクシデントマネジメントが不十分であったことが指摘されている。ここでは,同報告書等に依拠して,わが国ではシビアアクシデント対策が真剣に取り組まれてこなかったこと,そのため,わが国の原発は,ひとたびシビアアクシデントが発生した場合,放射線の被害拡大を抑えきれず,大惨事にいたる危険性を有していること,そのような原発を稼働させることは許されないことを述べる。
(1) シビアアクシデント(SA)とは,設計基準事象(DBE)を大幅に超える事象であって,安全設計の評価上想定された手段では,適切な炉心の冷却または反応度の制御ができない状態であり,その結果,炉心の重大な損傷に至る事象を指す。設計基準事象(DBE)とは,Design Basis Eventsの略で,安全対策をたてるために想定した事故のシナリオのことである。 「大幅」の意味は,設計基準事象(DBE)の範囲は超えるが設計上余裕を持ってつくられている範囲が現実には存在しており,その安全余裕によりカバーされる範囲をさらに超えたところが,「大幅に超える事象」とされる。世界の原発で,シビアアクシデントは,これまで3度発生している。1度目は,1979年の米国スリーマイル島原発事故であり,2度目が1986年に旧ソ連のウクライナで発生したチェルノブイリ原発事故であり,3度目が2011年3月11日に発生した福島第一原発事故である。
(2) アクシデントマネージメント(AM)とは,設計基準事象を大幅に超え炉心が大きく損傷するおそれのある事態が万一発生したとしても,それがSAに拡大するのを防止するため,若しくはSAに拡大した場合にもその影響を緩和するために採られる措置を指す。
(1) シビアアクシデントが真剣に議論されるようになったのは,1979年に発生したスリーマイル島原発事故(以下,TMI原発事故という)が契機である。1975年に公表されたWASH-1400(ラスムッセン報告)において,原子炉のリスクのほとんどは設計で想定した対策を立てた範囲を超える事故によること,その確率については当時信じられていた値よりも高いことが指摘されていたが,設計の範囲を超える事故など理論的にはありえても現実には起こりえないというある種の「信仰」が支配していたと言われている。そのような信仰を打ち砕いたのはTMI原発事故であり,この事故を契機に世界中でシビアアクシデントの現象の解明や対策が研究されるようになった。この動きに拍車をかけたのが1986年のチェルノブイリ原発事故である。1980年代後半からアクシデントマネジメントが先進国で整備され始めた。
(2) 米国では,1985年の「過酷事故政策声明」に基づいて,1988年にはSAに対する脆弱性を発見するための個別プラントの解析の実施を事業者に要求し,さらに1991年には外部事象(地震,津波,火山の噴火などの自然現象や航空機事故,テロ等の人為的事象)のPSA(確率論的安全評価)の実施を求めている。その中で米国の原子力産業界はシビアアクシデント・マネジメントガイドラインを作成し,各事業者に対してそのガイドラインへの適合を拘束力ある形で要求し,1999年には全事業者でAMの整備が完了した。欧州では,チェルノブイリ原発事故による放射性物質汚染を経験したこともあり,放射線リスクから環境を保護することが規制上重要な目的の一つと認識され,格納容器ベント系にフィルターを設置する等の対策がとられた。たとえばドイツでは,1986年12月に原子力安全委員会がフィルター付ベントの設置に関する勧告を出し,既設原子炉への配備が行われ,フランスにおいても,1989年までに,サンドフィルターを使用した原子炉格納容器ベント系が各発電所に配備された。ここでフィルター付ベントについて説明しておく。ベントとは,原子炉の損傷等で原子炉から発生する膨大な水蒸気で格納容器の圧力が上昇したとき圧力を下げるために格納容器内の水蒸気をベントラインと呼ばれる配管で外部に放出することを言う。格納容器の圧力を下げないとやがて格納容器は圧力に耐えられず爆発して中にある大量の放射性物質をまき散らしてしまう。格納容器は,止める,冷やす,閉じこめるという原子炉制御の最後の砦である。ベントには,水で満たされた圧力抑制室を経由するウェットベントとドライウェルを経由するドライベントがある。ウェットベントは水の中を通すことで放射性物質が低減するが,ドライベントの場合は,放射性物質を帯びた蒸気がそのまま大気中に放出される。これを防ぐために欧州等では,ベントラインの終端に巨大なフィルターを取り付けることで,ベントラインを経由して放出される放射性物質の量を,元の1/100~1/1000へ低減させる仕組みが取られている。これがフィルター付ベントである。福島第一原発では,1号基と3号機でウェットベントが行われ成功したが,2号機ではウェットベントは不成功におわり,ドライベントが試みられたが成功したがどうかは不明とされている。日本ではフィルター付ベントを備えた原発はない。現在(2012年5月),大飯原発の再稼働の条件の一つとして,将来ベントフィルターを設置することがあげられているが,これは遅まきながら欧州等の例に習おうとしたものである。
1982年8月,通産省は,「原子力発電安全対策のより一層の充実(セーフティ21)」という声明を出した。1992年5月,原子力安全委員会は,「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネジメントについて」という決定を出し,その中で「原子炉設置者において効果的なアクシデント・マネジメントを自主的に整備し,万一の場合にこれを的確に実施できるようにすることは強く奨励されるべきである」と指摘した。1992年7月,通産省は,原子安全力委員会の上記決定を受けて,「アクシデントマネジメントの安全規制上の位置づけ」を発表し,アクシデントマネジメントは,法的な拘束力のある規制措置ではなく電気事業者の自主的措置として整備していくことを事業者に要請した。 電気事業者の自主的措置とした理由として, ①厳格な安全規制により我が国の原子力発電所の安全性は確保され,SAの発生の可能性は工学的には考えられないほどに小さい。②AMは,これまでの対策によって十分低くなっているリスクをさらに低減するための,電気事業者の技術的知見に依拠する知識ベースの措置で,状況に応じて電気事業者がその知見を駆使して臨機にかつ柔軟におこなわれることが望まれる,を挙げている。
①のような楽観論・「安全神話」が,法的な規制を見送り,電気事業者にアクシデントマネジメント対策にまじめに取り組みをさせなかった最大の要因である。その後,各電気事業者は,PSAを実施し,その結果をもとにAMの候補案を出して,1994年3月にその結果を通産省に報告した。通産省は同年10月,それらをとりまとめた「軽水型原子力発電所におけるアクシデントマネジメントの整備についての検討報告書」を発表し,その中で概ね2000年を目途として運転中の全原子力発電所にAM対策を整備するよう促した。これを受けて電気事業者はAM整備に取り組み,2002年3月末にすべての原子力発電所施設においてAMの整備は完了したとされる。2002年4月,原子力安全・保安院は「アクシデント・マネジメント整備上の基本要件について」を発表した。その後事業者は,PSAを用いた個別プラント評価を実施してAM対策の有効性を評価し,2004年3月までに原子力安全・保安院に対してその結果を提出し,保安院と原子力安全委員会は基本要件に基づいて評価し,その妥当性を確認したことになっている。わが国の沸騰水型原発で曲がりなりにもベント系が整備されたのはこのような流れの中においてであった。
(1) 真剣さの不足
このように整備したはずだったのに,福島第一原発事故では,アクシデント・マネジメントは十分機能しなかった。その背景には,TMI原発事故,チェルノブイリ原発事故を経た後も,それら事故の場合は,「日本とは原子炉の型が違う」「原子炉の核反応の特性や制御棒に欠陥がある」「原子炉格納容器がない」「運転規則違反があった」「運転員が操作を間違って緊急炉心冷却系を止めてしまった」などの理由を挙げて日本ではシビアアクシデントは起こりえないとの「安全神話」があった。上記のとおり,1992年7月の通産省の発表した方針で,アクシデントマネジメントについての法的規制を見送り,事業者の自主的措置に委ねた理由として,シビアアクシデント発生の確率は工学的には考えられないほど小さいという認識があった。シビアアクシデントの発生はほとんど無視してもいい確率でしかないということであり,これも「安全神話」である。このような認識のもとでは,真剣な対策などなされ得べくもなかった。
(2) 電源喪失時のアクシデント・マネジメントの備えの不足
福島第一原発の事故でアクシデントマネジメントが機能しなかった原因として,具体的には,全電源喪失により,プラントパラメーターの監視ができなくなり,格納容器ベントに手間取ったことが挙げられている。1,2号機では津波到来直後から,3号機では12日の深夜から13日未明にかけて直流電源を喪失し,原子炉水位等の重要なパラメーターが測定できなくなった。計器は逐次復旧されたものの,重要な意思決定の場面でプラントパラメータを参照できなかったことがアクシデントマネジメントを非常に困難にした。例えば1号機の水位計が回復したのは,炉心損傷が生じたとされる時刻の後であり,この時まで水位計の信頼性は大きく損なわれていた。原子炉水位の計測が継続しているか,シビアアクシデント後にも信頼性を保てる計器が備えられているかすれば,当直や現地災害対策本部は,より早く1号機の深刻な事態に気づいた可能性がある。また,制御用の電源や圧縮空気の不足と,劣悪な作業環境(照明の喪失,高い放射線,高温)が原因となって,原子炉格納容器ベント作業に多大に時間を要した。また,ベントラインの構成完了後にも,ベント弁がたびたび閉止したことから,再度弁を開ける作業が必要となった。一方,欧米には,ベント弁をシャフト(軸)で接続し,かなり離れた場所から操作できるように工夫されたベントラインを持つ原子力発電所も存在する。ベント弁の操作性が高ければ,ベント作業に要する時間が短縮され,ベント作業に携わった作業員の被爆は低減されたと考えられる。また,原子炉格納容器が設計最高圧力より高い圧力を受ける時間は短くなることから,原子炉格納容器から外部へ漏洩する放射性物質の量や,水素の量が低減した可能性がある。格納容器ベントは準備されてはいたが,地震と津波という複合災害の中ですみやかにベントが行えるほどの準備はされていなかったのである。
(3)水素爆発への備えの不足
福島第一原発では,1号機,3号機,4号機の原子炉建屋で水素爆発が起きた。炉心溶融により水素が発生し,その水素に何らかの発火源がふれると水素爆発を起こすことは予見できた事態であるから,水素爆発の防止は,アクシデントマネジメントの重要な柱である。原子炉格納容器については水素爆発に備えて窒素を充満させて爆発を防ぐなどの対策がとられていたが,原子炉建屋での水素爆発はこれまでほとんど考慮されたことがなく,対策は採られていなかった。
(4)内部事象への対応に限定されたAM,最悪の事態を想定せず。
わが国で,従来,事業者により検討され整備されてきたAMは,内部事象への対応にほぼ限定されてきた。内部事象とは,機器の故障や誤操作のことを指す。シビアアクシデントに至る原因としてこのような内部事象しか想定してこなかったということである。福島第一原発のシビアアクシデントの原因は,機器の故障や誤作動ではなく,地震とそれに伴う津波であった。このような自然現象は外部事象という。外部事象には,自然現象以外に航空機事故やテロなど人為的な事象も含まれる。全電源喪失(SBO,ステーション・ブラックアウト)に対するAMも,内部事象に起因するSBOを対象としており,地震及び津波という外部事象に起因するSBO対策は,一部を除いてほとんど機能しなかった。外部事象起因のSAに対するAMの整備には,外部事象についてのPSAが不可欠であるが,90年代には信頼に足る評価手法が確立されていなかったため,研究を継続的に実施して外部事象へとPSAの範囲を拡大していく,という方針が示されていたにすぎない。事業者の自主措置としてのアクシデントマネジメントは,一通り整備は行われたものの,外部事象へ範囲を拡大してこなかった。そのため地震,津波という自然災害に起因するシビアアクシデントに対するAMに不備をきたすことになったのである。地震や津波によって原子力発電所の諸設備,機能がどのような影響を受けるのかを考慮した上でのアクシデントマネジメントは策定されていなかった。「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」(1990年8月30日策定)では「短時間のSBOに対して,原子炉を安全に停止し,停止後の冷却を確保できる設計であること」(指針27)とされていたが,「長時間にわたるSBOは,送電線の復旧または非常用交流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はない。非常用交流電源設備の信頼度が,系統構成又は運用により十分高い場合においては,設計上SBOを想定しなくてもよい」(同解説)とされていた。なお,「短時間」とは概ね30分と考えられていた。この指針が誤りであったことは今や誰の目にも明らかである。地震や津波の場合には,福島第一原発の場合がそうであったように,送電線の復旧にも非常用交流電源の修復にも長時間を要する事態が容易に生ずる。福島第一原発の場合は,まず,地震及び地震による土砂崩れにより,送電塔や開閉所(発電所で発生した電力を電力系統へ送り出すために設置される中継基地のこと),変電所が損傷し,東京電力新福島変電所(6系統)及び同富岡変電所(1系統)からの外部電源をすべて喪失した。その直後,福島第一原子力発電所の非常用ディーゼル発電機が起動し交流電源は一時的に回復したが,約40分後に襲来した津波によって,ディーゼル発電機の一部,発電機の冷却システム(水冷式のもの)及び接続先の配電盤が浸水し,1~5号機でSBO状態に至った。事業者が整備していたSBO時のアクシデントマネジメントは,内部事象を起因とするものであり,非常用ディーゼル発電機の故障機器復旧や隣接する原子炉からの電力融通を主な対策としていたが,前者は津波によって使用不能となり,後者についても,複数の原子炉がほぼ同時にSBO状態に陥ったため,有効に機能しなかった。つまり地震や津波によってSBOになることは想定していなかった。その結果,SBOに引き続き炉心溶融,格納容器の破壊の危機に直面したのであるが,そのような事態に対する対策は持っていなかった。そのような事態はそもそも想定していなかった。「指針」でさえもSBOは30分以内に修復できると考え,長時間のSBOに引き続く炉心溶融,格納容器の破壊など想定していなかった。そのような事態は起こりえないという「安全神話」があった。
以上は福島第一原発事故についてのものであるが,被告の浜岡原発の場合も,同じ政府の方針の下にアクシデントマネジメントを策定したことから,東京電力の場合と同様の指摘が当てはまると考える。地震,津波など外部事象に起因するSBOに対する対策が不十分であること,炉心溶融,格納容器破壊という最悪の事態を想定した対策がないこと,原子炉建屋の水素爆発対策がないこと,ベントフィルターがついていないこと等を指摘しておく。
関連して,免震重要棟とオフサイトセンターの問題について触れておきたい。
(1) 免震重要棟
地震による原発事故の場合,現地に対策本部を設置する必要があるが,対策本部として予定する建物が地震で損壊してしまっては対策本部を設置することもままならない。そこで,震度7の地震に襲われても,会議室,通信設備,電源設備,空調設備などの機能が損なわれないように免震構造を採用した鉄筋コンクリート造りの建物を免震重要棟という(免震事務棟ともいう)。免震重要棟は,新潟県中越沖地震で柏崎刈羽原発の緊急対策室の建物入室扉が開かなくなり,初動対応に支障を来したことを教訓として建設されることになった。福島第一原発事故でも免震重要棟は事故対応の作業拠点として重要な役割を果たしている。浜岡原子力発電所にも免震重要棟は建設されているが,その高さが2階で約10メートルしかないため,21メートルの津波が襲来した場合,使用できなくなる可能性がある。
(2) オフサイトセンター
また,株式会社JCOのウラン加工工場における臨界事故を教訓として,原子力災害時に,国,都道府県,市町村等の関係者が一堂に会し,国の原子力災害現地対策本部,地方自治体の災害対策本部などが情報を共有しながら,連携の取れた応急措置を講じ,防災対策活動を調整し円滑に進めることの必要性が認識されるようになり,それに対応するものとして,原子力災害対策特別措置法第12条1項により主務大臣が指定する施設として,緊急事態応急対策拠点施設がもうけられた。これがオフサイトセンターと呼ばれるものである。浜岡原子力発電所の場合も御前崎市役所に隣接してオフサイトセンターは設置されているが,その場所は,原発から約2.3キロ,海岸線から約1.5キロ,標高12.0メートルの地点にあり,原子力災害が発生し場合,建物が放射線を浴びて関係者が立ち入れなくなる可能性が高く,また,21メートルの津波で機能喪失する可能性もある。
1 昨年の東京電力福島第一原子力発電所の過酷事故や,その後の浜岡原発の運転停止の事実で明白になったことは,原発がなくても,火力発電,水力発電による電気を多少なりとも増加させれば電気は不足しないという事実である。昨年,東京電力は東北電力の電力不足に電気を融通していたし,中部電力も又,浜岡原発の運転停止をしている中で,関西電力に電気を融通し,さらに,今年に入って,九州電力への融通を加える状況である。電力会社が今までベース電力を原子力発電,水力発電とし,変動する電力需要に追従して出力を上げたり下げたりする役割を火力発電に与えており,原子力発電を重視し,火力発電を軽視してきた。
2 東海原発が運転を開始した前年の1965年から現在までをとって考えてみても,真夏の最も暑い時(午後2時頃から3時頃)に記録される最大消費電力量(ピーク電力量)でも,火力発電と水力発電を合計した発電設備容量を一度も超えていないということである(下図参照)。
(「図解 原発の嘘」小出裕章 扶桑社 より)
すなわち,原発がなくとも,火力発電と水力発電のみで日本の電気は足り,電力不足は発生しなかったということである。実際,電力事業連合会の公表している電力統計情報により,発電設備容量と最大消費電力量を対比すると,1997年以降は2010年までは,一度も原子力発電を必要とするデータは記録されていない。特に,中部電力の場合は,他の電力会社と比べ,原子力発電に依拠する割合が低く,2008年度実績で総発電量に占める原子力発電の割合が15パーセント(経済産業省「電源開発の概要」2008-09等)であり,浜岡原発を再稼働させなければならない状況は発生していない。
3 国や電力会社は,原子力発電をベース電力とする根拠に,原子力発電によるコストが他の発電,特に火力発電のコストより安価であると主張する。国の公表した2004年の「原子力発電四季報」による発電以外は,原子力発電(40年稼働として計算)が1kwhで5.3円,石炭火力発電5.7円,LNG火力発電6.2円,石油火力発電10.7円,水力発電(稼働率45パーセント)11.9円である。これをみる限り,原子力発電のコストが最も安価であることになるが,これには「カラクリ」がある。原発を維持するには,核燃料税,原発設置自治体への協力寄付金等の支払いがあるが,上記原子力発電の1kwhあたりの発電コストを算出するにあたっては,上記の「社会的費用」が全く計上されていない。大島賢一立命館大学教授は,この「社会的費用」を考慮して原子力発電の発電コストを試算しているが(静岡県防災・原子力学術会議「原子力経済性等検証専門部会」,2012年1月31日),これによると,1970年から2010年までの40年間で原子力発電の発電コストが1kwhあたり9.78円で,火力発電のそれは9.37円になり,原子力発電のコストが火力発電のそれを上回ることになるという。この計算には,使用済み核燃料の処理費が含まれていないので,これを考慮すると原子力発電のコストはもっと高いものになる。このように,発電コストの面からみても,原子力発電を維持する必要はなく,他の自然エネルギーに転化していく必要がある。
以上
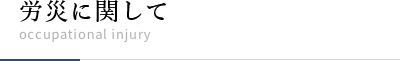
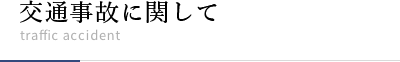
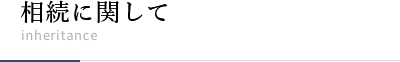
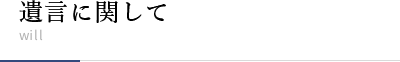
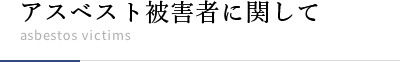
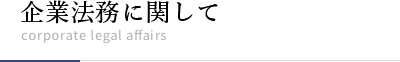
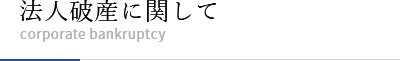
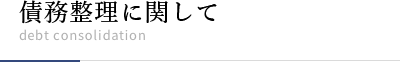
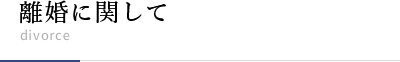
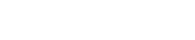
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348
平日法律相談 09:00 - 17:30 土曜法律相談 10:00 - 16:00